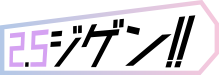2020年6月27日(土)、講談社とOffice ENDLESSの共同プロジェクト「ひとりしばい」のvol.1上演が配信された。
出演は荒牧慶彦。タイトルのとおり、「ひとりしばい」だ。本番の前に行われるゲネプロもオンライン。ここでは、このプロジェクトの概要と公演の様子をレポートする。
講談社×Office ENDLESSによる「ひとりしばい」プロジェクトとは?
新型コロナウイルスの影響により、大小問わずさまざまな演劇の興行が中止になっている。
そんな中、最大限「NO!!3密」を意識したうえで、「キャスト・スタッフらに活動の場を作りたい!」「舞台に立つキャストの姿をお客様に観てもらいたい!」という想いから、講談社とOffice ENDLESSの共同プロジェクトが実現した。
「ひとりしばい」はタイトルのとおり、キャスト1名による一人芝居だ。豪華な演出家とタッグを組んだ、完全オリジナルストーリーが届けられる。
稽古はオンラインミーティングアプリ「Zoom」などを活用しておこなわれ、観劇は配信課金システム「ファン⇄キャス」、会場は池袋に誕生したLIVEエンターテインメントの複合施設ビル「Mixalive TOKYO」(ミクサライブ東京)の「Hall Mixa」を使用。
撮影方法などはそれぞれの回によるので、実際に視聴して楽しんでほしい。同じ「ひとりしばい」の企画であっても、まったく違うものが観られる。
また、いわゆる「舞台に1人で立って芝居をする一人芝居」なのかと聞かれれば、それはネタバレになってしまうため、やはり実際に観てもらうしかない。
以下レポートは、みどころをメインとして、できるだけバレに触れないようにしている。しかし公式写真とともに軽くストーリーも紹介しているため、まっさらの状態で観劇を楽しみたい人はここで引きかえし、観劇後に復習としてレポートを読んで欲しい。
個人的には、舞台設定やキャラの名前なども何もかも知らない状態で観劇し、ストーリー展開とともに内容をつかんでいく方をおすすめする。
リアルとフィクションが入り混じる世界観。12台のカメラが1人の男のすべての顔を映し出す
vol.1は荒牧慶彦による「断-DAN-」。作・演出は「朗読劇 私の頭の中の消しゴム 」などを手掛ける岡本貴也だ。舞台作品はもちろん、テレビドラマ、映画の脚本・監督、小説の執筆も多数おこなっている。
スーツ姿の主人公が目覚めるのは、閉塞感のある小部屋。どこかの地下室のようでもあり、秘密基地のような雰囲気もある。生活感はなく、快適な時間を過ごすために整えられた環境でもない。
背後には「外出禁止」「徹底した消毒のお願い」といった、ざわりと胃の底をなでるような心当たりのある文言が書かれた張り紙がされている。

カメラ(こちら側)に向かって語りかけるときもあれば、そこに何も無いようにうろうろと部屋中を動き回ることもある。
外とまったく「断」たれているわけではなく、電話やSNS、インターネットで外界とは「繋」がっている。電話やSkypeで外部の誰かと通話していることから、人が死に絶えた世界ではないのだなと分かる。

彼はなぜ、何の目的でここに1人でいるのだろうか。そしてここはどこなのか?
セリフのはしばしから徐々に状況が読めてくる楽しさは、オリジナルの脚本ならではだ。
場所が分かり、そこが「打ち捨てられたかのようなどこか」だと理解した瞬間、なぜそうなってしまったのという理由も含めて、観劇ファンにとっては胸にぐっとくるものがあるだろう。
用意されたカメラは12台。画面は、映画やドラマのように次々に切り替わる。ワンテイクの生配信芝居だということを忘れてしまうほどの画作りだ。
この芝居における「カメラ」の役割にも注目してほしい。彼の姿を追うシステムとしてのカメラだけではなく、配信ツールを通して見ているからこそ、秘密の場所で何かしている姿を覗き見している気持ちになる。

荒牧の演技は、高く低く打ち寄せる波のような感情を途切れさせない。怒り、悲しみ、喉が焼ききれるほどに怒声を放ったかと思えば、電話の向こうの相手にびくびくと怯えた顔を見せる。

この芝居の脚本にある字数は12000字にもわたったという。12000字といえば、文庫本に換算すると30ページほどにもなる。それだけのセリフを、はじめはモノローグを読み上げるように淡々と、ときに子どものようにはしゃぎながら、そしてあふれる激情のまま口にする。
ワンシチュエーションだからこそ、ひとことのセリフも聞き逃せない。ラストシーンのダブルミーニングには、思わず涙があふれることだろう。

映画と演劇の境界が曖昧になった演出・脚本を、ひとりの熱量で演じ切る
本公演の後には、アフタートークの時間がもうけられた。一人芝居を演じ切り、綺麗な顔立ちに汗びっしょりの荒牧と、作・演出の岡本がマイクを持って舞台に立つ。
開口一番「つかれたぁ!」と荒牧がどさりと椅子に座りこみ、トークの時間が始まった。50分喋りどおしで、身も心もヘトヘトになったことだろう。
今回の企画は、演者から演出家を逆指名したものだ。「俳優として貴重な体験をさせていただいたけれども、クレームを入れたい。こんな(大変な)脚本になるとは思わなかった。稽古日数から予想していた5倍の分量だった」と笑いを誘った。
「電話の向こうにも人はいない。だから、すべて自己発電で熱を作っていかないといけなかった」。1人の芝居でこれだけの熱量を伝える荒牧慶彦の、役者としての力をあらためて感じた。
岡本は「映画と演劇の境界をものすごく曖昧にしたかった」と語る。映画やドラマなどの仕事も多く手掛けてきた彼ならではの演出だ。
タイトルの「断-DAN-」は、一文字で「1人での孤独さ」を表しているという。芝居の中での、ストーリー上の孤独と、自粛期間中の孤独を意味している。
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、演劇人たちがひとつになった部分もあり、断絶されてしまった部分もある。こうして、取り戻せないものや複雑な繋がりをないまぜにした脚本ができあがった。
今だからこそできる芝居を。「やれる範囲」に妥協しない、新しい演劇の形
2020年3月から、演劇界は大きなうねりに飲み込まれている。公演の中止、延期を余儀なくされ、公演の発表がされることもなく白紙になった舞台も多いことだろう。
そんな中、無観客配信、YouTube・Zoomなどを使った配信など、さまざまな工夫が重ねられてきている。今できる範囲での妥協ではなく、制約を逆に取った新しい表現方法が生み出され始めていると感じる。
公演は、本番一発の配信のみ。アーカイブの配信は6月29日(月)~7月6日(月)まで。配信ならではの映像の荒さもドキュメンタリー的で魅力があったが、クリアな画面でもぜひとも観てみたい。
広告
広告