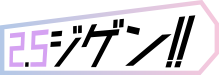2022年1月22日(土)、本格朗読演劇 極上文學シリーズ第16弾「ジキルとハイド」が新宿・紀伊國屋サザンシアターで開幕する。
本シリーズは、日本文学における名作を立体的に表現する朗読劇×演劇のスタイルの舞台で、今回で10周年。過去には宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」、谷崎潤一郎の「春琴抄」などが取り上げられており、今回は初の海外作品「ジキルとハイド」(ロバート・ルイス・スティーヴンソン著)が上演される。
2.5ジゲン!!では、2019年の第14弾(第15弾は新型コロナウィルスの影響により中止)に続き本作に出演する梅津瑞樹にインタビューを行い「極上文學」への思い、前回の公演で得られたもの、学生時代の思い出に至るまで話を聞いた。

――今回の参加が決まられた時のお気持ちはいかがでしたか。
極上文學シリーズへの参加は、2019年の第14弾「桜の森の満開の下~孤独~」以来になりますね。2020年4月に第15弾「桜の森の満開の下~罪~」の公演が予定されていたのですが、新型コロナウイルスの猛威で中止になってしまいました。その15弾では、14弾で演じた鼓毒丸ではなく、ツミ夜姫を演じることになっていましたので、中止になってしまい残念ですというお声をファンの皆さんからいまだに頂いています。僕自身もツミ夜姫を演じるのを楽しみにしていたので、中止はとても残念でした。
こうして極上文學の世界に、空白の一度はあれど、3度目の参加をさせてもらえるのはありがたく思っています。しかも今回は、前回の会場である四方向からの囲み舞台の新宿FACEではなく紀伊國屋サザンシアターなんですよね。櫻井圭登くんが出演していた第13弾の「こゝろ」(2018年12月)が上演されていたのもこのサザンシアターでした。観に行って大変衝撃を覚えたので、この劇場で上演されるバージョンの極上文學に出られるのはとても楽しみです。
――前回出演されたご感想をお聞かせください。
世に“朗読劇”は数あれど、極上文學は頭一つ抜けていると感じました。この数年のコロナ禍の中で、朗読劇の新たなスタイルが模索されながら上演されてきたように感じますが、極上文學は10周年、今作で第16弾という実績があり、スタイルを確立していますね。もはや朗読劇というよりは極上文學というジャンルではないかと。
多くある朗読劇と極上文學との違いを挙げると、朗読劇は音としての言葉にウエイトがあるように感じますが、極上文學では言葉はもちろん、肉体におけるウエイトが非常に高いです。
例えば、手にしている本は枷(かせ)でもあり演出としてうまく生きる瞬間もあります。肉体の表現も含めて多くのことを考えなければ、ただ本を持って歩いているだけにもなりかねません。

――本のページをめくる動作も表現の一つだと感じました。
ページのめくり方について細かい指示はありませんが、そこには各々役者の個性が表れていましたね。時には、ずっと本を見ずに相手の芝居を受けてこちらも芝居を続けていたら、いざページをめくろうとした時に数ページ飛んでしまっていたなどということもありました(笑)。付箋を付けてめくりやすくしてはいるのですが、全然違うページをめくっていたりもします。でも芝居中なのでそこはうまくごまかしつつ…(笑)。
前回は四方向を囲まれている劇場だったこともあり、めくり方にしてもほんのちょっとした動きにしても、どの角度からも常に見られている緊張感がありました。普通の舞台よりも考えることが多かったかもしれません。
――今回はシリーズ初の海外作品となります。
海外の作品には、僕らが日常会話で使うものとは少し違う言葉が出てきたりしますよね。僕自身海外戯曲をやるのは初めてなので、実際に台本を頂いて読んでみないと分からないことだらけです。セリフがどう訳されるのか、どういう言葉を使っていくのか…。
でも、構成や根幹とするものはこれまでと変わらないように感じます。語り部が俯瞰で物語を語り始めるのは極上文學ならではのスタイルですね。演出のキムラ真さんがどういうアプローチをしてくださるのかな? と楽しみにしています。


――共演経験のある方もいらっしゃいますね。
大崎捺希、樋口裕太、碕理人さん…それから後藤恭路にはびっくりしました。捺希と恭路とは今年(2021年)の夏に共演したのですが、また一緒にやれるのは嬉しいです。捺希は振り切ったお芝居ができる人だと思っていますし、楽しみにしています。
――前回の極上文學に出演したことで新たな発見はありましたか。
体の使い方をことさら意識するようになりました。ダンスは苦手なんですけれども、体の動かし方についてはよく考えています。体で遊ぶというのでしょうか。終電後などの夜中に知らない街をふらふらと歩いて、すれ違った人たちをモーフィングするのが好きなんです。
以前、洗濯機のない部屋に住んでいたのでコインランドリーに通っていて、その道すがら「30秒歩いたら他の人として歩く」なんていうテーマを課して歩いたりもしていました。ダンスは苦手ですけれど、そういう“遊び”で体を動かすのは楽しいですね。
前回の公演では四方を囲まれている舞台だったからこそ、より体の表現を意識しました。今回はキャパシティも大きくなるので、また表現方法が変わるかもしれませんね。

――ジキル博士が抱えていた闇の部分のように、ご自身でも「自分のここは好きではない」と感じる部分はありますか。
そんな部分しかないです、すぐに人を妬みますしね(笑)。周りの人たちはみんな自分にないものを持っているのに、なぜ自分は何も持っていないのだろうと思います。もちろん皆さんも同じようにそう思っているのでしょうけれども、僕は人一倍そのような気持ちが強いです。でも、そういう妬みや怒りのような気持ちが表現をする原動力になっています。
その気持ちもいずれは枯渇するのではと聞かれることもあるのですが、驚くことに29歳になってもなくなる気配は全くありません。生涯付き合っていくのかもしれませんね。
――梅津さんは小説好きでもいらっしゃいますが、特に好きな作家はいますか。
ヘミングウェイは初めて読んだ中学生の頃からずっと好きです。自分もここに住んでみたいと思ってしまうほどの街の描写や空気感…実際には住みたくないですけれども(笑)。それからカフカや安部公房は一通り読んでいます。

――学生時代から小説を書かれていたと伺っています。
僕に関するWikipediaには「文学部」とあるのですが、実はそうではなく芸術学部なんです。その中でも文芸を専攻していたので、もっぱら“書くこと”をしていました。とは言っても全然大学へは行かず、家で映画ばかり観ていたり、大学へ行っても空き教室でサークルの仲間たちとやっぱり映画を観たりしていました(笑)。
そのサークルは自分で立ち上げたのですが、仲間たちは演劇なんてやったことのないやつらばかりだったのに、戯曲を借りてきて読んだり、その場で芝居をしてみたりもしましたね。空間芸術のグループ展をやったりもしました。
今も、機会があれば個展を開きたいなとはずっと思っていますし、いいタイミングがあれば小説もと思っていますが、なかなかスケジュールが難しいですね。
――最後に、今作の見どころを教えてください。
もし極上文學を観たことがなくても、「本」というメディア自体が好きな人にはとても楽しんでいただけると思います。手にしている台本が、ただ開くだけではなく何にでもなり、そこには役者各々の使い方の違いも出てきます。
今作での見どころは、シンプルにジキル博士とハイド氏の対比でしょうか。この2人が入り混じり入れかわる瞬間をぜひ楽しみにしていてください。
取材・文:広瀬有希/撮影:ケイヒカル
広告
広告