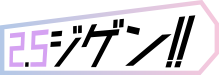2020年2月21日(金)開幕の舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇FINAL~POWER OF BIKE~。坂道たちにとって2度目のインターハイがついにゴールを迎える。
『ペダステ』といえば、演出家・西田シャトナー氏による独特の表現方法が有名だ。
観劇するうち、そこにない自転車が見えてくる『ペダステ』。シンプルな舞台装置と役者の体でシチュエーションを表現する「パワーマイム」や「パズルライドシステム」といった表現手法を確立させたのも、西田氏である。
2.5ジゲン!!では『ペダステ』の演出・脚本をつとめる西田シャトナー氏に、開幕を直前に控えた最新作「新インターハイ篇FINAL~POWER OF BIKE~」についてインタビューをおこなった。
総北、箱根学園、京伏、呉南。4チームそれぞれのカラー

――『ペダステ』では高校生たちの熱い闘いが描かれます。演じる俳優たちにもチームごとにカラーがあるかと思いますが、それぞれどんなチームですか?
西田シャトナー(以下、西田):チーム総北は、常に楽しそうに見えてじつはかなりストイックに芝居をしている印象です。
どのチームもストイックなんですが、総北はとくにキャプテンの鯨井さん(手嶋純太役・鯨井康介)の性格が反映されているんでしょうか。
いつも真摯にものづくりに取り組むという姿勢が徹底しているように思います。根底ではふざけない姿勢というか。
――鯨井さんのそういった性格がチームに影響を与えている?
西田:楽しくするのも大切なんです、雰囲気が悪くなれば怪我にも繋がりますから。
鯨井さんは常に楽しく現場を盛り上げながらも必ず仲間や作品のために動くという、そんな生真面目さを持った俳優です。そういった鯨井さんの性格をチームのみんなが尊敬しているように感じます。
初演からずっと、演じてくれたメンバーはみんな真面目な方々ばかりですが、とくに鯨井さんの代になってから、総北、あるいはカンパニー全体に、彼の真面目さがすごく染み込んでいる気がする。それが僕はとても好きです。
――箱根学園チームはいかがでしょうか?
西田:チームハコガクは、文学的なことを理解するチームだなと感じます。キャプテンのターくん(泉田塔一郎役・河原田巧也)は、ちょっとかわいい性格をしていて、楽しいことが好きなんですけれど、必ず時間を見つけては静かに原作を読み込んでいます。
そして原作の中から、しっかりと物語の芸術性やテーマを見つけてくる。そういうところをハコガクらしいと感じたりもしますね。トミー(葦木場拓斗役・富永勇也)も随分今回の脚本には意見をしてくれました。
脚本や演出の原作読み込みのミスを指摘してくれることもハコガクメンバーは多いです。
――京都伏見の皆さんはいかがですか?
西田:京都伏見は、林野さん(御堂筋翔役・林野健志)が、役柄上はキャプテンではないものの俳優たちの間ではキャプテンの立場で引いてくれています。
林野さんは常に現場全体を見渡して、「自分たち(京都伏見チーム)がどうあれば物語が豊かに進んでいくか」という点を考えてくれている。
彼はいつも奥から全体を見渡して、誰かが困っていたら必ず助けに行きます。控室でも、他の俳優の演技の相談にのっていることが多いです。
これは小鞠役の天羽くん(岸神小鞠役・天羽尚吾)も似たところを持っています。そして阿部ちゃん(水田信行役・阿部大地)も2人に引っ張られてそういう一面を見せている。
京都伏見というチームは、原作では最も抜け駆けをしそうだったり、あるいは全体を敵視して闘うチームですよね。
でも『ペダステ』の現場の中では、じつは京伏がカンパニーのみんなを見てくれている安心感があるんです。静かに全体の役に立とうとしてくれるというか。
――三者三様のチームカラーなのですね。
西田:そうですね。ハコガクがわちゃわちゃと楽しんでいたり、総北が真面目にやっていたりする中で、彼らの仕事が増えて余裕がなくなってくると京伏が助けたり。
それはたまたまかもしれないけれど、チームごとのキャプテンのカラーが反映されているんでしょうね。
――呉南についてはいかがでしょうか。
西田:呉南の栗原大河くん(浦久保優策役)は『ペダステ』初参加で、かつ浦久保も初登場のキャラクターです。
呉南チームは今回彼ひとりなので、「周りに頼るわけにいかない」と本当にまじめに、一生懸命取り組んでいます。誰かに助けてもらうのを待たずに、自分の仕事を黙々とやっている印象が強いです。僕の知らないところで、きっと他のメンバーが助けているのかもしれませんが。
14作目を迎える『ペダステ』。心に浮かぶ思いとは?

――『ペダステ』シリーズ14作目となる今作ですが、過去の公演を経ての思いをお聞かせください。
西田:僕はどの作品も「これ1本が人生にあればいい」という気持ちで毎回作ろう、と思っています。だから基本的に「14作目だから、どう」というふうには思いたくないんです。
もしも今後の人生、自分がお芝居を作れなくなったとしても「この1本があって良かった」と言える作品にしたいと。実際はそんなふうにきっぱり割り切れないけれど、常にそう思い定めて作ろうとしていますし、今回もそんな作品にできていると思います。
――なるほど。
西田:……ただね。最近ちょっと心に浮かぶのは、なんというか、まるで……劇団時代のときにも到達できなかったことが、このカンパニーでは叶い始めているなという思いなんです。
僕は2000年まで10年間劇団をやっていましたが、10年やるとやはり蓄積されてくる豊かさがあるんですよ。最初は単純に友達だからと組んだチームでも、3〜4年やっていくうちにそのチームでしかできないことができ始めていく。
技術面や芸術面でも蓄積が共有されますし、精神面でも、世間から否定されそうなことでもそのチームでなら乗り越えていけるという勇気が湧いてきたりとか、「俺はもうこいつに褒められたら納得がいく」というような思いが湧いてきたりとか。
――時間の蓄積あればこその現象ですね。
西田:『ペダステ』を始めた頃というのは、僕にとって慣れない商業演劇でしたし、いろんなところから来た俳優さんとともに短い期間で一緒にやるんだ、という感覚だった。
だから当時は「ずっと走らせ続けることは難しいから、半分はスロープを動かすことで足をためよう」とか「劇団時代なら何も持たずに自転車を表現したけれど、ここではハンドルだけは使って少し演じやすくしよう」という、そういった発想で作っていきました。
でも、気がつくと『ペダステ』はスタートから8年が経ち、劇団時代にも到達できなかった場所が見え始めてきている気がする。それは役者だけではなく、各セクションの方々や、音楽を作ってくださるmanzoさんとのチームワークもあればこそです。
このチームワークだから、できることがある。その愛着が僕の中ですごく甘やかなものになってきていて、今そこに葛藤も生まれているんです。


▲全ページ、びっしりとメモが書き込まれた西田氏の台本
――「葛藤」というのは?
西田:「この1作品だけ」と思い定めてストイックに作らなくては、という思いと、この幸福を味わいたい、噛み締めたい、という思いとが毎日せめぎ合っているんです。
年月を積み重ねて『ペダステ』のカンパニーに湧き始めた豊かさが、ついに自分の中の信念を揺さぶり始めたというか、僕を癒そうとしてくるというか。
――それは、とても激しい葛藤ですね。
西田:ただ、たとえば地球に生命が誕生するときも、雷と高温の海と、酸性の雨と電圧の中で、緑が生まれて美しい風景が出現し、穏やかなときが訪れたんですよね。
だから、頑張って生命を生み出そうともがく時代にこだわらずに、生まれた後の豊かさも味わったらいいのかもしれない……なんて思ったりもするんですけど。
今はまだ答えが出ないままに本番が迫ってきています。
――終わってみないと分からない部分もありそうですね。
西田:そうですね。
この幸福が本物だということは感じるので、後から思い出すときにはちゃんと豊かに思い出したい。ただし、それで自分が甘くならないように気をつけようと日々思っているところです。
『ペダステ』8年間で、印象に残るエピソードは?

――これまでの『ペダステ』の現場で、印象に残っているエピソードは?
西田:今でも思い出すのは、初代の小野田坂道を演じた村井くん(村井良大)のエピソードです。ある日、本番の幕が上がる前に、僕自身なんともいえない不安に襲われたことがありまして。
――理由のない不安ですか?
西田:そうです。嫌な予感というんでしょうか。
もう5分後には幕が開く状態なのに「本番中にトラブルが起きたらどうしよう、危険なことがあったらどうしよう」という急激な不安に襲われながらスタッフ通路をひとり歩いていたら、なぜかそこに村井くんが待っていたんですよ。
つい、「みんなを頼むよ」と声をかけたら、彼が「シャトナーさん、任せてください」と笑顔で言った。その姿を見て「ああ、小野田みたいだな」って思ったんです。
ピンチのときに、気がついたら立ってる奴がいるな……という、あの感じ。本当に小野田みたいだった。
じつはこれ、他のキャストにもよく感じるんですけれども。
――ピンチのときに誰かがそこにいる、という。
西田:ええ、原嶋くん(鏑木一差役・原嶋元久)とかにもよく思います。稽古をしていて「ここどうしようかな」と思っていると、原嶋くんがなぜかそこにいて、ナイスなことをしてくれる。
初代・銅橋役の兼崎さん(兼崎健太郎)もそうでした。兼崎さんは、僕がみんなに「どう伝えたらいいかな」と悩んでいるタイミングで不思議と「みんな集まれ」って集合をかけて、適切なアドバイスをしてくれていた。
役者たちもよく言っていましたが、しんどい出番を終えて舞台袖に入ると、もうそこに兼崎さんが待っていると。それと同じようなことを、演出家の僕も俳優のみんなに対してよく感じます。
いてほしいところに、奇跡みたいに誰かがいる。もしかしたら、演出家が俳優に助けてもらうなんてことはあってはいけないのかもしれないけれど、実際によくあるんですよ。そういうことが起こり得ているカンパニーなんですね。

――今回のキャスト陣の中では、原嶋さんがとくに多いですか?
西田:いえ、みんながそうです。多いという点で言えば、鯨井さんとたーくんがやっぱり多い。2人は毎日そんなふうに動いてくれています。
そして新キャストの岸本さん(銅橋正清役・岸本卓也)も多いですね。僕が「うーん」と悩んでいると、岸本さんが不思議とそこにいて、何か意見を言ってくれる。
新メンバーがそうしたことを頻繁にしてくれるというのは、不思議な感覚でもあります。
――素敵なカンパニーですね。
西田:はい、大好きです。僕は人付き合いというものがあんまり得意ではないけれど、そういう人間でもこの幸せなカンパニーの一員として参加できているということが、本当にありがたいです。自分に自信を持てるような、そんな気持ちにさせられています。
演出家・西田シャトナーから、2.5次元ファンに伝えたいメッセージ

――最後に、『弱虫ペダル』新インターハイ篇FINAL~POWER OF BIKE~に向けての意気込みと、2.5次元を愛する観劇ファンの方々へのメッセージをお願いします。
西田:2.5次元作品のファンの皆さんは、目の前にあるものの向こうに「目の前のものが描こうとしている何か」を観る力を持っている人たちだと、僕は思います。
ステージ上に物理的には出現させ得ないものを「本当は何を描こうとしているのか」と見つめることができる、そういう想像力を持った人たちだと思うんです。
これは、漫画ファンはみんなそうなんですよね。紙の上にインクで描かれたものだけではなく、その向こうにあるものをみんな見ている。そのイマジネーションの力は、全ての物事において最も大事だと思うんです。
その力があるから、人類が「これを擦れば火がつくな」と知恵を働かせることもできるし、バラバラの人間でもチームになれば強くなれるよということも想像できる。
そんな素晴らしい力を持っているのが、2.5次元のお客さんだと思っています。
その素晴らしいことを楽しく経験できる場として、しっかりお芝居を作っていきます。今回も、そして今後も、ぜひ楽しみに観に来てください。

舞台『弱虫ペダル』新インターハイ篇FINAL~POWER OF BIKE~の東京公演は2020年2月21日(金)~23日(日)天王洲 銀河劇場にて、大阪公演は2020年2月27日(木)~29日(土)大阪メルパルクホールにて上演。
また、大千秋楽はRakuten TVでLIVE配信と見逃し配信が実施される予定だ。詳しくは公式サイトまで。
ひとつのクライマックスを迎える『ペダステ』。原作ファンも観劇ファンも、ぜひこのステージを体験してほしい。
広告
広告