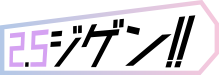横井翔二郎が出演する映画『ザ・ミソジニー』が、9月9日より東京・シネマカリテより全国で順次公開される。
本作は『リング』『呪怨』『霊的ボリシェヴィキ』等で知られるジャパニーズホラーの立役者・高橋洋が手がける最新作で、夏の山荘で行われる芝居の稽古を通して恐怖の出来事が描かれる。
2.5ジゲン!!では、脚本・監督を務めた高橋と、主人公ミズキのマネージャー・大牟田役を演じた横井に対談取材を実施。本作の見どころや撮影時の様子などを聞いた。

――映画『ザ・ミソジニー』公開を間近に控え、現在の心境を教えてください。
高橋:僕は今ちょうど公開準備や取材に奔走している真っ最中で、作品を振り返るというよりは、現在進行系で走り続けている感じですね。
横井:映画そのものが完成しても、そこで終わりではないですもんね。僕にとっては、試写会で挨拶させていただけるような大きな役で映画に出るのは初めての経験でした。クランクアップから約1年経ち、無事に公開できることを実感してホッとしています。
――今作の見どころ、注目してほしいシーンはどんな所ですか?
高橋:まずは、ファーストシーンです。このシーンは今回のロケ地となった山荘を見た瞬間にパッとひらめいたものなんですが、撮影しながら「これは自分にとっても未知の作品になるぞ」という手応えを感じましたし、今作の内容を象徴するシーンにもなっています。
横井:開幕から見どころって、すごくイイですね。
――横井さんの思う見どころも教えてください。
横井:見どころを紹介するのってなかなか難しいんですよね……。どの作品でもそうなんですが、僕は演じ手が決めるのはもったいないというか、観てくださった人が体感して持ち帰った印象=その作品の見どころだと思っているので。ただ、出来上がった今作を自分が観て感動したところを挙げるなら、なんといっても「画(え)のパワーと美しさ」です。仄暗い画面でありながらも鮮烈な美しさがキープされ続けるので、美術品を観賞するようにじっくり堪能してほしいです。あとは、すでに試写会を観た方の中には深く考察してくださる方も多いですね。感想を読んでいると「一度観ただけでこの考察が出てくるのはすごいな」と驚くような意見も多く、楽しませていただいています。ホラーと言っても大きな音でドキッとさせられるタイプの作品ではないので、「びっくりする系のホラーが苦手」という方にもおすすめしたいです。
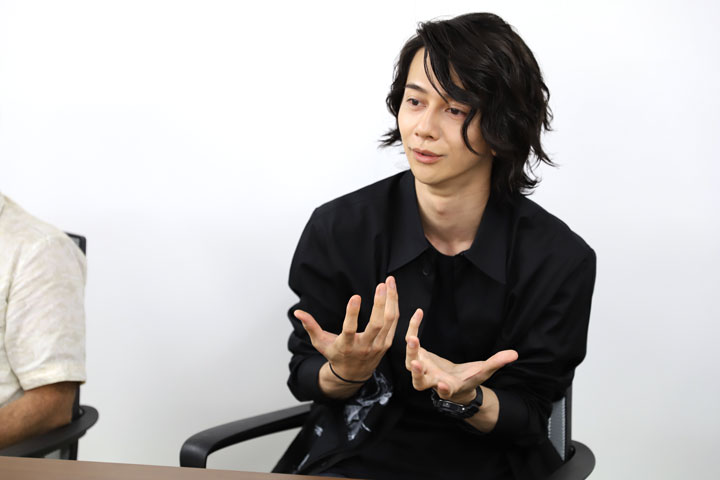
映画で得た「鮮烈な経験」は舞台でも活きる
――普段、舞台で多く活躍されている横井さん。映像作品と舞台ではどんな違いがありますか?
横井:まず、お芝居している最中に視界に入っているスタッフさんの数が段違いです。舞台の稽古で視界に入るのは数人〜多くても十人前後。演出家さん、演出助手さん、演出部の方が数名、音響さん……という感じです。一方、映画の撮影では「○○役のサポートをする人を、そのまたサポートする人」という具合で、常に大人数が協力し合ってシーンを作っています。この人数の差に最初は驚きました。それから、舞台では目の前の人に向かって芝居をすることがほとんどですが、映画はそうではない。目の前に相手がいない状態でセリフを言うことも珍しくありません。「これは想像力が試されるぞ」と思いました。僕は舞台ではどんどん動いて人に絡んで熱量を高めていくタイプなので、人のいないところに向かってお芝居するという感覚を掴むまで苦労しました。
――演じ手としては、環境が大きく異なるのですね。
横井:演技については「やりすぎてしまう」というのも自分の課題でした。オーバーになってしまうというか、大きな声を出す、分かりやすい表情をする、というのを無意識にやりすぎてしまうんです。それは映画と舞台の違いとしてよく話題にされることですが、自分の映像をチェックしたときに「なるほど、こういうことか」と実感しました。でも、悩んだことも含めて本当に良い経験をさせていただいたと感じています。だって、この経験を今後の舞台作品に持っていけたら最強ですよね。『ザ・ミソジニー』の撮影はトータルで10日間くらいと短期間でしたが、僕の人生の中で非常に濃厚かつ鮮烈な経験でした。
――その後、ご自身のお芝居に変化があったと感じますか?
横井:はい、それは確実にあると思います。舞台だからって大げさにやりすぎる必要はないんだ、と気づきましたし。もちろん現場によっては求められるものが変わるので、随時スイッチを切り替える必要はあります。でも今回の撮影で得たマインドは、今後の自分にとって大きなプラスになるはずです。自分の引き出しと呼ぶにはまだ未熟なので、これからさらに磨いていけたらと思っています。
重要なシーンで魅せた、横井の「芝居の底力」
――高橋監督が今回、横井さんをキャスティングされたきっかけは?
高橋:大牟田役の俳優さんを探している中で、スタイリングディレクター(衣装担当)の藤崎コウイチさんから「この人の芝居を見てみてほしい」と紹介されたのがきっかけです。舞台『12人の怒れる男』で横井さんが演じた陪審員4号という役を見て、「自分が探していたのはこの人だ」と感じ、出演をお願いしました。横井さんのお芝居には絶対的な底力を感じましたし、どんなに難しい役でも「この人ならきっと受け止めてくれる」と確信しました。
横井:ちなみに、『12人の怒れる男』で僕の髪は長かったですか、短かったですか?
高橋:長かったです。
横井:あっ、じゃあ1年目の方ですね。あの作品は2年連続で出演させていただいていて、役作りの点でもすごく思い入れがあります。「どんなキャラクターに見せたいか」というのを自分の中で1から構築して、それこそ髪の長さひとつとっても考え抜いて作り上げた役なので、あの作品を見て評価していただけたことはすごく嬉しいです!
高橋:横井さんは芝居のレンジ(幅)が広くて、たくさんの引き出しを持っている役者さんですよね。実際、『ザ・ミソジニー』の撮影中もそれを実感しました。たとえば撮影の終盤、横井さん演じる大牟田が内面深くに抱えたものをさらけ出すシーンを撮った際には、こちらが想定していた表現のラインを超えて「ここまでいってしまうのか」と驚くような演技を見せてくださったんです。そのときは徹夜の撮影で全員ヘロヘロになっていたので「はいOK」という感じでさらっと流してしまったんですが、後日編集の木田龍馬くんと映像を編集しながら、2人でそのショットを見て「本当にすごいね」「横井さんは絶対出世する」と盛り上がりました。
横井:このエピソード、試写会で初めて聞いて跳び上がりそうになりました。こんなに褒めていただけるなんて想像もしていなかったので、もう本当に嬉しくて。ありがとうございます。

――他にも、撮影中に印象的だったエピソードはありますか?
横井:あの、撮影中にめちゃくちゃ大雨が降った日がありましたよね。あれは雨を狙ってロケに行ったんですか? それとも……。
高橋:完全にアクシデントです。あまりにも土砂降りになってしまったので、屋外での撮影を急遽変更してロッジの中のシーンに切り替えましたね。
横井:アクシデントだったんですね。でもあの雨がまた、いい感じに作品に味を加えてくれましたよね。だから僕、もしかしてこの天気を狙ったのかなと思っていました。
高橋:たしかに芝居を邪魔する雨ではなかったですね、不思議と。
――アクシデントも作品に活きたんですね。
高橋:まあ、撮影にアクシデントは付き物ですから。
横井:アクシデントも味方にしてなんぼですね。そこは舞台と変わらないかもしれません。
高橋:僕は舞台の世界についてはあまり知らないんだけど、やっぱりアクシデントがあるんですか?
横井:いっぱいありますよ。段取りにないことが起きたり、置いてあるはずのものが定位置になくて焦ったり。でも舞台の場合、アクシデントが起きても物語を繋げられるようにと稽古を重ねていますし、役者もアクシデントが起きると「余計に燃える」という人が多いかもしれません。
高橋:なるほど。想定外のことがあったほうが活気づくというのは、映画の撮影でもよくあります。そこは通じているんですね。
横井:役者としてはどんな状況でも面白いものをお届けしたいし、そういう意味ではアクシデント=腕の見せ所なのかと思います。極端な話、公園で衣装も小道具もなく身体ひとつでやったお芝居が面白かったら、それはどこでやっても面白いはずなので。
高橋:横井さんはわりと、そういうところで肝が据わっていますよね。
横井:本当ですか? 僕、公演初日はいつも緊張で手の震えが止まらないですよ。
高橋:そうした繊細な面もありつつ、窮地に陥ったときには開き直れる強さも持っていらっしゃると思いますよ。僕ね、今回お任せした大牟田は、俳優さんにとって極めてやりにくい役だったと思うんです。ロジカルな解釈を組み立てることが難しいし、たとえ横井さんから「このシーンはどういう意味ですか?」と訊かれても、僕自身にも言語化が難しくてなかなか答えられないので。横井さんからしてみれば、わけの分からない脚本を渡されて明確なアプローチ方法も示されず、「とにかくやってみてくれ」と言われる状況なわけでしょう。脚本家として、監督として、もし「プライドを傷つけられた」と怒らせてしまったらどうしよう……と最初は緊張しましたよ。
横井:いやいやいや、滅相もないです!(笑)
高橋:だけど、本読み(出演者同士の読み合わせ)を終えた横井さんの第一声は、「あっ、これはつまり“分かんない”ってことですね」というものでした。明確な理屈で説明できない役なんだ、輪郭をパキッとつけなくていいいんだと、1発で割り切ってくださったんですね。僕はあのとき、すごくホッとしました。「ああ、この精神で臨んでくれるのであれば大丈夫だ」と安心しましたし、そこからはもう横井さんに委ねてしまいました。
横井:その辺りの感覚は、2.5次元作品で培われたのかなと思います。アニメやゲームの世界観って、現実とは全く異なる理屈であることも多いじゃないですか。そういう世界で生きているキャラクターに血肉を流し込む過程では、何か分からないことが起きてもそのまま受け止めることも大事なので。独自のルールがあっても「この世界はこういうものなんだ」とありのまま飲み込み、理解し、受け止める。さまざまな作品を通してそんな習慣が身についていたので、分からないことは「分からないんだな」と受け止めればいいと思えたんです。
高橋:非常にありがたかったです。
横井:高橋監督は、役者から「これはどういう意味ですか?」と質問されたとき、逆に「あなたはどう思います?」って質問返しすることがあるんです。僕はそれがすごく素敵だなと感じていて。世の中の出来事は全部理屈で説明できるわけじゃないし、作品づくりは未知の領域に飛び込む作業なわけだから、演じる側も細かい説明を求める前に「これはどういうことなのか」「自分はどう解釈するのか」と自分なりに考え抜くことが大事だと思います。そういう意味で、こちらを信じて委ねてくださったことは嬉しかったですし、大きなやりがいがありました。
撮影現場は、ホラー現象も受け流す忙しさ?
――高橋監督といえばジャパニーズホラーの火付け役。今作『ザ・ミソジニー』もホラー作品ですが、日常でホラー体験をしたことはありますか?
高橋:僕はいっぱいありますけど、仕事柄あちこちで聞かれる質問でもあるので、むしろ横井さんの体験を知りたいですね。
横井:いや〜僕、そういう経験が本当に全く無いんですよ。お化けも神様も、存在は信じているんですけどね。理由は「いたら面白いから」なんですけど。見えない世界も存在する、って考えたほうが面白いので。
高橋:ちょっと意外ですね。俳優さんって結構みなさん、ホラーな体験談持っていらっしゃる印象があって。
横井:そうなんですよ、わりとみんな持っているのに僕はゼロで……(笑)。劇場にはそういう話が多いし、怖い話で知られる所で仕事をしたこともあるんですが、とくに何も起きませんでした。『ザ・ミソジニー』はホラー映画ということで、今回は僕も何か経験するかなあと思っていたんです。現場はやっぱり独特の雰囲気だし、ロケ地は夜になると本当に真っ暗だし。……ですが、全然ありませんでした!(笑)もしかしたら、考える余裕がなかっただけかもしれませんが。
高橋:ああ、なるほど。たしかにホラーの撮影現場って不思議な現象が結構起きるんですけど、あまりにも忙しいからみんなサッと流しちゃうんですよね。
横井:それどころじゃない、ハイじゃ次○時からー! みたいな。
高橋:そうそう(笑)。『ザ・ミソジニー』の現場でも、他の役者さんが変なものを見ちゃう出来事があったんですけど、そこに浸ってる時間もなければ余裕もなくて、スルーして進行してしまいました。
横井:お化けのほうも、驚かそうとしてバッと出てきたのに「なんだ、全然こっち見てくんないじゃん……」ってガックリしちゃうかもしれませんね。
「人生に何かを刻む作品、ぜひ体感し尽くして」
――ご自身の中で、今後「こんな作品を作ってみたい」という夢や目標は?
高橋:『ザ・ミソジニー』では、物語の関節を思いっきり外す試みをしました。これは結構ギリギリまでできたなという手応えがあって楽しかったですし、その感覚も掴めました。もしまた今作のようなワンセット&ミニマムな作品を作る機会があったら、今回とは正反対のもの、つまり緊密でカチッとした構成の、舞台作品に近いようなものを作ってみたいですね。
横井:僕は、演じることはもちろんですが、何らかの形で「ステージをつくること」にチャレンジしたいです。先日『オドルンパッ!企画vol.4「グルメ戦隊 クラックスW」』で、生まれて初めて演出家として舞台作品に参加させていただいたんですが、そのときの感覚がもう衝撃的で。自分の頭の中で考えた画が他の役者さんを通して現実に浮かび上がった瞬間、すさまじい高揚感を覚えたんです。エンドルフィンが出まくって、ものすごく幸せな気分になって。初舞台に出演したときは頭のずっと奥で雷が鳴る感覚を味わいましたが、そのときとも全く違う、生まれて初めての感覚でした。自分の中から溢れ出す、ずっしりと重い高揚感、幸福感に全身を包み込まれるような……。これはすごいぞ、と思いました。ですので、何か「ステージ上で0から1をつくること」に絶対チャレンジしてみたいです。どんな形になるかはまだ想像もつかないんですが、それが今ひとつの目標になっています。
――最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。
横井:『ザ・ミソジニー』は、観るたびに感想が変わるかもしれない、そんな映画です。もしかしたら何度観てもモヤモヤと掴みどころがなく「難しい」と思うかもしれない。でもそれも今作の大きな魅力です。何度も観て、必死になって考えてたどり着いた答えすら、正解かどうか判断できないかもしれない。でも、人生に何かを刻むのってそういう作品だったりしますよね。今作を観て何かを感じたら、ぜひその感想を誰かとシェアしてみてください。僕に送ってくださるのももちろん大歓迎です。作品を受け取って、それを土台にして誰かとコミュニケーションをとる、それこそがアートの本質なんじゃないかなと僕は思います。観賞はもちろん、そんなコミュニケーションも含めておひとりおひとりが今作を「体感」し尽くしていただけたら最高に嬉しいです!

取材・文 豊島オリカ
広告
広告