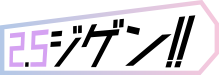東京2020パラリンピック開会式の演出を担当したウォーリー木下が今年初めて挑む演劇が、舞台「僕はまだ死んでない」だ。
死は時として、突然やってくるが、人は終わりの瞬間を見つめたとき、本人が、そして、周りがどう感じ、何を考えるのか。そんなテーマを、時にシリアスに、時にコミカルに描く。
舞台の開幕を前に、この作品の狙いとともに、東京パラリンピックを経て感じる舞台の可能性、将来について聞いた。
案外、身近なテーマ
――舞台「僕はまだ死んでいない」は、病に倒れ、身体が動かせず、意思疎通がとれない男性が主人公です。終わりの瞬間を見つめる主人公と、彼を取りまく人々の思いが交錯します。身体が動かせないということで、表現方法が制限され、演劇としては難しそうに見えますが、なぜ、このテーマを選んだのですか。
僕的には、難しいものだという認識はそんなにありませんでした。こういう作品が世の中にあった方がいいだろうと思って原案を書いたので、やりがいはありますね。
――こういう作品があった方がいいと思ったのはなぜですか。
日本において、ここ数年、終末医療、安楽死、命の選択といった話がニュースとしては出てきますが、実際にそれを議論する場は少ない。演劇、アートの表現の中で、そのことを解決しようとする取り組みみたいなものもあまりないので、必要だと思いました。
僕自身の身内に、終末医療の何かがあったというわけではありません。でも、今から僕にやってくる問題で、考えておかないといけないと思っています。それを、この題材をきっかけに考えさせてもらっています。
たぶん、多くの人も同じように遠い存在の話だと思うんですが、いずれ必ず身近なことになります。案外、身近に感じてる人が周りにいるので、この作品がそういう人たちと話すきっかけになればいいと思っています。
――このテーマを取りあげることになった具体的なきっかけはあったのですか。
写真家の幡野広志さんの文章を読んだのが一つのきっかけでした。血液がんで、ご自身で安楽死のシステムを調べ、意見を述べている人です。そして、医療の現場において『死ぬ』という選択肢が今の日本にはないということを問題にしていました。
ちょうどこの題材を考えているとき、ALS (編注:全身の筋肉が衰える難病「筋萎縮性側索硬化症」)の方が殺害される事件がありました(編注:依頼を受け、京都市内の自宅で薬物を投与した疑いで医師2人が2020年7月に逮捕された)。
こうした事件が起きるたびに考えることがありました。例えば、患者さんや障害を持ってる方が死ぬという選択肢を取りたいとなった時、日本にはいま、自殺かイリーガルの方法しかありません。イリーガルである以上は、黒い部分がたくさん関わってきてしまうので、幸せにならないと思うんです。
今回の作品と直接は関係ないんですけど、そういう命の選択について考える必要があると感じています。どう生きるかと、どう死ぬかには、きっと繋がっているんだろうな、と。
VR演劇をやって分かったこと
――新型コロナウイルスが収まらない状況で、舞台自体の開催が危ぶまれる状況が続いています。人々はコロナの中で、「生」について以前よりも考えるようになった状況ですが、ご自身は作品との向き合い方は変わりましたか。
コロナだからなのか分かりませんが、僕も50歳になり、残りどれだけ作品を作れるだろうと考え出しました。そのとき、演劇は、人と人との出会いで作品自体が大きく変わることが多々あるので、一緒に演劇を作りたいな、一度お会いしたいなと思う人たちと早くやっていかないといけないと思っています。
――あと何作品できるなどと考えるのでしょうか。
具体的に言うと、頑張ってあと20年だと思うと、やりたい作品を毎年1,2本やったとしても40本ぐらいかなと思います。40本やれれば本望ですが。でも、本数ではなく、なるべく長いスパンで、自分の後輩、子どもたちにつながるようなものを生み出していきたい。そっちのほうに興味が向いています。
――今回の舞台は、最初はVR(バーチャル・リアリティー)を使った演劇で行われました。VRでやったからこその発見はありましたか。
コロナの中で劇場が閉まった時に、演劇のようなものを配信で作りたくてVRを選びました。僕としては、観客が自分の見たいところを見られ、そこに臨場感のある映像があり、演劇に近いものが作れたと満足感はあります。
一方、できあがったものを見た時に、映像では、役者さんの気配が伝わらないことに気づきました。VRをつけているから、横を見たら役者はいるんです。見てみて『いたんだ』とわかるんですけど、舞台を見に行って、あまりそういうことはありません。台詞を発していなくても、下手からトコトコトコッと出てきたら、『なんとなく出てきたな』と見ていなくても感じられます。
そして、『生の情報量って膨大なんだな』と気付きました。つまり、人が発する謎のエネルギーがあって、画面を通してではどうも伝わらない。画面からは出てこない何か、ホルモン、エネルギーがあった。そのことに気付けたのがすごく良かった。つまり、生でやらないとこの要素は伝わらないんだと。
逆に言うと、生の良さというのは、ただ、そこに役者がいるからいいということではなく、役者さんが出しているエネルギーがあって、お客さんも出しているエネルギーがあって、それが混ざり合って空間ができている。概念としては分かっていましたけど、よりはっきりと分かりました。
――演出は変わりましたか。
それは変わらないです。やっていることは間違っていなかったんだと思いました。
パラ開会式で意識した「つなぐ」
――昨年のパラリンピックの演出は、言葉がなくても、世界の人たちに分かる演出でした。今回の舞台も、話せない人が登場します。以前から言葉を使わないノンバーバルのパフォーマンスをやってきていますが、何かができないことが、逆に表現の広さにつながっている印象があります。
以前と考え方が、変わってきました。昔は『しゃべらない』という足かせをつけることで、ルールという枠組みを作る。その中で、ものを作り、パフォーマンスをすることの面白さを考えていました。ゲームとか遊びとかスポーツとかが、ルールが明確になればなるほど、面白くなっていくのと同じ考え方です。
昨年、パラリンピック開会式の演出を担当し、また別のいくつかの仕事を経験して、例えば、歩けないとか、目が見えないとか、耳が聞こえないとか、しゃべれないということが、ルールというより、そのことによって生まれる自由を楽しめる人たちがたくさんいるということがわかりました。それは演劇にも応用できます。ノンバーバルの演劇で、いままではルールの中の遊びを面白がっていましたが、実はルールの中の自由さを楽しんでいたことに気付きました。
東京パラリンピック開会式でデコトラの一番前にいた武藤将胤さんはALSで体が全く動かないし、会話は視線入力で行います。彼と話していて、僕が知っている人の中でも、特にアイデアマンで、いろんな自由な発想があります。ALSという難病にかかり、治る方法が今はなかったとしても、これから先同じような病気になった人が楽しいと思えるような世界にしたいと話していました。
その発想の転換がすごい。ALSに限らず、寝たきりの老後をおくる人たちのためとか、赤ちゃんのためとか、人間なんてなんでもできる人の方が少なくて、何もできない人たちのための未来を作ろうとしていると考えていました。頭の構造が自由すぎて、ちょっとびっくりしているぐらい。すごいんですよ。
――東京2020は開催の是非をめぐって、国内のみならず、世界が分断されました。「片翼の小さな飛行機」を演じた和合由依さんの場面を含め、東京パラリンピック開会式の演出には「つなぐ」という意識が随所に垣間見えました。そういう意識はあったのでしょうか。
ありました。片翼の飛行機の女の子が自分1人で意識改革して、空を飛び立つのではなくて、へんてこなロックバンドの人と出会ったり、車いすの上で踊っている人と出会ったりして、変わっていくということにしたかった。
世界中から聞こえてくるリズムとか、その場所にいるアスリートたち。無観客にはなりましたけど、アスリートのみなさんの力強いエネルギーをもらって飛び立つ。平たい言葉で恥ずかしいですけど、1人ではないんだ、人と人がつながることで、何かをなしえることができるんだと。
でも、本当は、別になしえなくてもいいんですよ。つながることで、見える何かを体験してほしいということがありました。
当時は、世の中がネガティブな世界でした。でも、本当はもっとコミュニケーションを取りたい人たちがたくさんいる。『明るい方が本当はいいですよね。みんな』ということに気づけたことは大きいかもしれません。
――兄が障害者で、ずっと障害者の存在は身近でした。国際パラリンピック委員会のフィリップ・クレイブン前会長が以前、「パラリンピックで環境だけでなく、心が変わる」と話していましたが、障害者の家族がいる身として、障害者に縁遠かった人の心は変わったと感じますか。
ムードは大きく変わったと思います。バリアフリーは、人の心のバリアフリーが一番大きいと思います。そこが少しだけ、日本でもスタートしそうだなという予感はあります。でもこれをよりもっと具体的にどうしたらいいか。例えば目が見えない人がいたときにどう対応したらいいのかちょっと日本人はマニュアル、ノウハウがないと手をさしのべにくい。
だから、そういうものをもっと知らしめていくようなことをしないといけない。当たり前だけど、それをみんなに広めていく必要があると思うし、2022年はそれが始まる年なんだろうなと思います。
演劇のマジックを信じて
――舞台「僕はまだ死んでない」は2月17日から東京の銀座・博品館劇場で始まります。今はどんな心境ですか。(取材は1月中旬に行われた)
稽古が始まって、役者さんの声でセリフを聞くと、思っていたものと違ったり、逆に思っていたより、もちろん面白いと思うところも多かったり、始まって楽しいという気持ちがほとんどですね。
――不安はありますか。
僕がどれだけできるんだ、という不安はありますけれども、すごく素敵なチームが集まってくれたので、僕が駄目でもみんなが何とかしてくれるはずです。なので、あんまり心配はしていないです。
――舞台の見どころを教えてください。
1時間半ぐらいのお芝居。見ている間は集中してその世界に入ってもらって、非現実の世界を楽しんでもらえたらと思います。たぶん終わる頃には現実ともつながっていると感じてもらえると思うので、演劇のマジックみたいなものを信じて、怖がらずに見に来てください。人生が変わるかもしれない作品になると思います。
ウォーリー木下の略歴
1993年、神戸大学在学中に演劇活動を始め、劇団☆世界一団(現sunday)を結成。役者の身体性に音楽と映像とを融合させた演出を特徴としている。ノンバーバルパフォーマンス集団「THE ORIGINAL TEMPO」のプロデュースでエジンバラ演劇祭にて五つ星を獲得するなど、海外でも高い評価を得る。2018年4月より「神戸アートビレッジセンター」舞台芸術プログラム・ディレクターに就任。東京2020パラリンピック開会式、手塚治虫生誕90周年記念「MANGA Performance W3(ワンダースリー)」やハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」などの演出を手掛ける。
「僕はまだ死んでない」とは
病に倒れ、身体が動かせず、意思疎通ができない。そんな状態で終わりの瞬間を見つめる主人公と、それを取り巻く人々の思いを描く作品。交わされる会話の端々には、親しい間柄、身近な存在ならではのユーモアや可笑しみが入り混じり、ときにはコメディな筆致で、人の命について描く。
ウォーリー木下は企画当初から【VR映像での配信】と【劇場での上演】の構想があったが、2021年2月、新型コロナウイルスの影響で有観客公演は困難な状況が続くことから、VR版が製作・発表されました。上下左右の全方位を撮影できる360度カメラを、舞台上で主人公が横たわっているベッドの上に置いて撮影することにより、主人公の視点そのものな“一人称”の映像を収録し、新感覚の演劇作品が生み出された。そして、2022年2月、劇場での有観客上演が行われる。出演は矢田悠祐 上口耕平 中村静香/松澤一之・矢吹真央 公式ホームページは、https://www.stagegate.jp/stagegate/performance/2022/bokumada2022/index.html
広告
広告