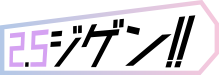10月30日(土)に彩の国さいたま芸術劇場で幕を開けた舞台パルコ・プロデュース2021『ザ・ドクター』。2019年にロンドンで発表された本作は、少女の死をきっかけに医療研究所のエリート医師が宗教・ジェンダー・階級格差などの問題を通して自分を見つめ直していく社会派現代劇だ。
日本初演となる今回、主演を大竹しのぶ、『ゲルニカ』を第28回読売演劇大賞優秀作品賞に導いた栗山民也が演出を担う。
2.5ジゲン!!では、若き医師マイケル・コプリー役で出演する宮崎秋人にインタビュー。『ザ・ドクター』の見どころや役との向き合い方、コロナ禍で改めて感じた役者という仕事についてなどを聞いた。
抱いた使命感「成長しなければ」
−−まず、この舞台のお話が来たときのお気持ちを教えてください。
手放しで嬉しかったです。ここまで役者をやってきて良かったと思いました。
演出の栗山民也さん、主演の大竹しのぶさんをはじめとして、いつかはご一緒したい方ばかりの中に、3年ほど前に共演させてもらって信頼できる橋本淳さんのお名前もあって…淳さんはすごく安心感を与えてくれる先輩なんです。
本当に嬉しかったし、この強いカンパニーの中に飛び込んで「ここで成長できなければ今後未来はない、成長しなければ」と思っています。

−−脚本を読まれてどのような印象を受けましたか?
栗山さんもおっしゃっていたのですが、作家さんの明確な答えが作品の中に書かれていなくて、問いかけで終わっているんです。物事には、ある程度の“正解”や少数派と多数派はあるけれど、どちらが正しいのか間違っているのかという答えはない…それを描いているのが面白いと感じました。
それから、イギリスの作品なのでセリフの言い回しが特徴的なんですよね。皮肉を言い合ったり、「ありがとう」と言っているのに相手のことをチクリと責めていたり(笑)。同じイギリスの方の作品である『PHOTOGRAPH51』(2018年)の時も思ったのですが、腹の底の探り合いというのでしょうか。
だからこそ、セリフで芝居しなければいけない難しさを感じます。舞台の上でその瞬間、生で感じないとやれない作品です。求められるものがすごく多いですし、目の前に立ちはだかっている壁は高いです。
最近、シェイクスピア作品もやらせていただいているのですが、表現の硬さという点で今回はシェイクスピアとは真逆のことを求められています。対極とも言える作品ですね。焦りはないですけれど、今ちゃんと自分のものにしてお芝居しないと、ここにいる意味はないと思っています。
−−主演の大竹しのぶさんとは初共演ですね。
普段はふわっとしていらっしゃる印象なのに、お芝居が始まった瞬間にがらっと別人に変わる方です。本読みで大竹さんが第一声を出した瞬間に「これはやばいかも…!」と背筋がスッと伸びました。多分、僕以外の方も確実に“のまれた”と思います。
これまで経験してきた現場では、座長についていくとか引っ張られるという感じだったのですが、今回は「気づいたら流れの中にいる」という初めての感覚です。大竹さんは本読みが始まる前は「分かんない」「難しい」なんておっしゃっていたんですけれど(笑)。

−−とても刺激の多い現場のようですね。
セリフを理解するために、本読みの後に翻訳の小田島恒志さんにたくさん質問させていただきました。腑に落ちている言葉とそうでない言葉とでは、差が明確になってしまうんですよね。分かっていない言葉を“分かっている風”にやる必要はない、嘘をついたらダメなんだと今回改めて痛感しています。
分からないことは分からないままにしないで、教えてもらってしっかりと自分の言葉にする。栗山さんも稽古の前のひとこと目くらいにそういうことをおっしゃっていました。
その栗山さんの求めていることを大竹さんは体現できる。だからこのお2人は何度も一緒に組まれているんだと刺激になりました。
−−カンパニー全体の雰囲気はいかがですか。
やわらかい雰囲気の方がすごく多いので、今はまだ本読みの段階ですが、時間が経つにつれてより和やかになるんじゃないかなと思います。僕の隣が床嶋佳子さんで、ご挨拶させていただいたらすぐに「秋人って呼んでいい? とこちゃんて呼んでね」っておっしゃってくださったんです。
あの場で僕がいきなり「とこちゃん」と呼んだら周りがびっくりすると思ったので「徐々に」とはお返事しましたが、早く「とこちゃん」と呼びたいですね(笑)。すごく優しい人が多いので、これから楽しみです。

今、自分には“芝居しかない”
−−コロナ禍の中で、役者として何か心境の変化はありましたか?
2020年の6月に公演予定だった舞台が中止になってポンと空いた時期に「自分は何者なんだろう」と考えることがありました。そんな時、演劇ユニット・第七世代実験室の方たちが、「YouTubeでリモート演劇をやるんだけど」と声をかけてくれたんです。ああ、また役者って名乗れるんだ…と救われた気持ちになりました。
それから、仕事をたくさんして忙しくしていないと、延々と家で映画を見続けたりしてダメになるなとも思いました。忙しい方が掃除も洗濯も料理もちゃんとしている気がします(笑)。
考え方がシンプルになりましたね。観て、求めてくれる人がいるから、応えたい。この地球に生を受けて、今自分ができることは芝居しかない。だから芝居をする。
一人でも多くの人に届きますようにと思って、舞台も映画もドラマもやっています。届かなかったら自己満足になってしまいますから(笑)。その中でも、舞台は自分の心のためでもあるように思います。
−−どんな点がご自身の心のためになるのでしょうか?
カーテンコールで拍手をいただくと、作品自体もですが自分も肯定してもらっているように感じるんです。この仕事をやっていて良かったなと思います。
上演中は客席のお客さまの顔を見て反応を確認する余裕はないんですけれど、特にダブルカーテンコールでは客席も照らされることが多いので、できるだけちゃんと一人一人のお顔を見ようと心がけています。定期的に直接拍手を頂くそういう機会がないと、勝手に自信をなくしてしまうんですよね(笑)。自分へのご褒美にはやっぱりカーテンコールが一番です。
映像の仕事や配信は、劇場での舞台では届かないところにまで色々なものが届けられます。まずは届ける、それが自分の仕事です。もちろんプロ意識を持ってやっているんですけれど、稽古している最中やカーテンコールでは、ああ楽しいなぁ…と喜びが勝ってしまいますね。もっと言えば、稽古や本番の後に飲みに行けたらもっともっと楽しいです(笑)。

−−俳優としての今後のビジョンを教えてください。
自分が一緒にやりたい人と、やりたい作品を作れるようになりたいです。これまで、色々な方と出会わせていただいて、今大好きな人たちがたくさんいます。舞台で主演という形ではなくても、例えば「栗山さんとまたやりたいです」と言えばまた呼んでもらえたり、何かやりたいとなったときに色んな方が力を貸してくださったら…。
「いいね、それやろうよ」って言ってくれる人が増えたらいいですね。そのためには、やりたいことを自分の中でたくさん貯金しておかないといけませんね。
でもその前に何よりもまず、今回のこの『ザ・ドクター』という作品の重みを感じています。抱えきれるかどうか分からないくらいの重みです。きっと今、成長期だと思うので、この作品で大きく成長しなければと思っています。
アイデンティティを大事に…
−−今回演じるマイケル・コプリー役へはどのようにアプローチしようと考えていますか。
今回の『ザ・ドクター』の作品としてのキーワードの一つに“アンデンティティ”があります。それは演じる俳優自身に対しても適用されていて、脚本の準備稿にも「演じる俳優さんのアイデンティティを大事に」と書いてありました。
「マイケル・コプリーはこういう人間だよな、だからこう演じたい」ではなくて、この身体と声で31年生きてきて、色んな経験をさせてもらった自分が演じるマイケル・コプリー、というのを大事にしようと思っています。
彼は、発する言葉や性格的に生意気な部分がありますけれど…いや、まぁ俺も生意気かな(笑)。若い医師である彼もここまでやってきた自信があって、僕も今回この舞台に立たせてもらうのは大きな自信になります。こじつけでもいいから、一つ一つを相違点だとは思わずに共通点として考えていけたら楽しく演じられるんじゃないかなと思います。

−−最後に見どころをお願いします。
内容については色々と仕掛けが多いので触れづらいんですけれど、若手医師以外の医者チームは年齢性別関係なくだいぶ対等に言い合うので、そこを観てほしいです。僕のことを知ってくださっている方には、「あいつ、あのメンバーの中で対等に言い合っているなぁ」と思って観てくださるだけでも楽しいと思います(笑)。
それから、みんながオブラートに包んで喋っている中、マイケル・コプリーは思ったことをストレートに思った瞬間にバツンと言ったり、気持ちを爆発させるタイミングもあります。そこは舞台の中でも異質な要素ですね。
淳さん演じるポール・マーフィとはチクチクやりあっているので、マイケル・コプリーとポール・マーフィのコントラストも面白いですよ。
取材・文:広瀬有希/撮影:ケイヒカル
広告
広告