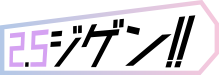劇団ナイスコンプレックス夏の風物詩、舞台『12人の怒れる男』が7月30日(金)に開幕する。60年前に生まれ、ワンシチュエーションでストーリーが進行する密室劇の金字塔である本作は、「物語は脚本が面白ければ場所など関係ない」という言葉を体現するとも言われている。
2018年の初演から4度目の上演となる今回も、劇団主宰で、脚色・演出のキムラ真が「芝居が大好きな役者」「一緒に芝居をしたい役者」にオファーをかけ、集まった役者たちが舞台に立つ。
2.5ジゲン!!では、陪審員1号役の東拓海と陪審員4号役の藤原祐規にインタビューを実施。3度目の「12人」出演となる東が振り返るこれまでのエピソードや、キムラ作品に数多く出演している藤原から見たキムラ真の芝居観、本作で求められている“純粋な芝居との向き合い方”などについて話を聞いた。
心に残る気迫のぶつかり合い
――お2人の初共演は、今作と同じくキムラ真さん演出の「極上文學13」(2018年)でした。当時のお互いの印象を教えてください。
藤原祐規(陪審員4号役):まず、「特徴的な声を持っているな」と感じました。芝居はとても真面目で、想いをひたすら届けたいという気持ちが強く伝わってくる。若き才能と出会ったな、と思いました。まさか後に、めちゃくちゃ頭のおかしい、暴走した芝居を見せられるとは思ってもみなかったです(笑)。

東拓海(陪審員1号役):実は、フッキー(藤原)さんと初めて共演させていただく前にリサーチをしていたんです(笑)。フッキーさんを知っている方に、「どんな方なんでしょうか?」とお話を聞いたりして。そうしたら皆、「とても素敵な先輩だから、甘えてもいいと思うよ!」とそろって言っていたんです。実際お会いしてみたらすごくやわらかい雰囲気の方で、「好き…」ってなりました(笑)。
フッキーさんは後輩に対しての壁が無くて、すごく話しやすいんです。後輩の心を助けてくれる先輩だ、と思いました。
――再共演は、これもキムラさん演出の「LIVEミュージカル演劇チャージマン研!R-2」(2020年)。東さんは主演の研役(4人の中の1人)、藤原さんは星くん役でしたね。
藤原:あの時はひどい目にあいました(笑)。その前にキムラ演出の別の舞台に拓海が出ているのを客席で観ていたんですが、頭のネジが外れた暴走した役を演じていました。それを、チャー研ではさらにパワーアップさせてきたんですよね。その時に研役で共演していた若井おさむさんも、拓海のことを「芸人でもこんな人おられへん」って言っていたくらい(笑)。
毎回あれだけブチ上げたテンションに持っていけるのはすごいですし、事前に用意したんだかその場で思いついたんだか分からないことを、ドンとやるのがすごいと思いました。
――そして今回の共演となります。過去を経て、今の印象はいかがですか?
東:4号のビジュアルを見た時に思ったのは、「こんなに似合う人がいるんだ!」ということでした。僕がフッキーさんに感じている“頭のいい先輩”というイメージがビジュアルと一致していたんです。
これは一緒にお芝居をしたらフッキーさんに見どころを全部奪われてしまうな、と感じるくらいに魅力ある4号で、改めてかっこいいなと思いました。

藤原:頭がいいと思われているのは、まだ化けの皮がはがれていないだけなので、そのままいきたいですね(笑)。
演出のキムラが今回の作品に対して、「ネタをやるのではなくて、お芝居の面白さで笑いをとりたい」と言っていたんです。その中で拓海がどう来るのか楽しみにしています。急に大声を出すとか、「どうした?」って思わずきょとんとしてしまうようなことをブチ込んでくるのか(笑)。逆に、そういうことを一切封印して演じるのか…何をやるのか予想がつかないのは、拓海が成長したからだと思います。
――東さんは3回目、藤原さんは初めての本作出演になります。お話が来た時のお気持ちを教えてください。
東:2020年の第3回公演が終わってから、DVDの特典映像か何かで「もう一度1号をやりたい」と話したんです。だから、今回また1号としてお話をいただいた時は素直にうれしかったです。
それと同時に、「もっと上があるんだぞ」「お前は今のままだけじゃないぞ」というキムラさんからの思いを感じて、いい意味での緊張感もあります。まだまだ1号としては完成に至っていませんし、慣れることも気持ちを緩めることもなく、今年も挑みたいです。長く味わっていきたい作品だと思っています。
藤原:お話が来た時は、あのうわさのやつだ…と思いました(笑)。この作品は、キムラの人徳もあってすごいメンバーがキャスティングされていますよね。その中に入れていただくのはプレッシャーもありますが、うれしいです。
上演が4回目なので、これまでの公演を超えたいという気持ちもあります。プレッシャーと楽しみな気持ちが、半々くらいですね。
キムラは自分が言っていることに熱が入りすぎて、すぐ泣くんですよ(笑)。大人になると人間は泣かなくなっていくものだと思うんですけれど、キムラは感極まってすぐに泣く。でもそれは、演劇が好きだから泣くんだろうと思うし、演劇愛あってこそですよね。
役者として、作・演出を信頼していきたいから、愛のあるキムラに対しては信頼を置いていますし、付いていきたいと思っています。拓海はキムラからの愛をすごく受けているなと感じます(笑)。拓海が「もう一度1号をやりたい」と言っていたのを覚えていてキャスティングしているんですから。
東:僕もキムラさんが好きです! その期待に応えたいと思っています。

――東さんは、過去の公演で強く心に残っているエピソードは何でしょうか?
東:前回の公演のことです。7号を演じられていた古谷大和さんが、感情をあらわにして声を上げるシーンがありました。それがあまりにも本気に見えてしまい、「やばい、止めなくちゃ!」という気持ちになったんです。
一生懸命に大和さんを止めたのですが、お芝居の中でこんなにも疲れたことはない…と、精神力も体力も使い果たしてへとへとになりました。本気の気迫を感じてぶつかり合いながら演じたあの時の出来事は、今でも心に強く残っています。
――役作りについて伺います。今回の作品も含めて、普段どのように役作りをされていますか?
東:最初は、自分と似ているなという部分を見つけます。俺もそういうところあるよな、と感じる分かりやすい部分を見つけて、次に違いを探していきます。俺はこういうことは言わないけれど、この人は言う…自分と何が違うんだろう? というように。
そして、そういう考えになるにはどうしたらいいのか? と考えながらアプローチしていきます。今回であれば1号は高校の先生なので、「授業中に寝ている生徒がいたらどうやって注意するかな?」ということも考えます。
藤原:いつもやっているのは、その人物が、何が好きで何が嫌いなのか、ということを考えることです。どこがどのくらい好きなのか? なぜ嫌いなのか、どこまで嫌いなのか? 今回の舞台で言えば、他の11人に対して4号がどう感じているのかを考えて、その人との関係性を作っていきます。
周りとの関係性を考えずに「きっとこういうキャラだ!」とだけ思っていると、相手が投げたとっさのボールに反応できないことがあるんです。フラットな状態で、相手のボールを見極めてからでも動けるようになること。そういう関係性はすごく大事だなと思います。

噓偽りなく全力で“噓をつく”
――大がかりなセットの無いワンシチュエーションの本作。“純粋に芝居と向き合いたい”という想いから上演されていると伺いました。お二人が考える“純粋に芝居と向き合う”とは、どういうことでしょうか?
東:芝居というのは、全力の嘘なんじゃないかなと思うんです。自分自身にも嘘をつくし、本心じゃないことも言う。でも、それを全力でやる。
ひょっとしたら、キムラさんが集めたキャストたちは、“嘘偽りなく全力で嘘をつける人たち”なんじゃないかなと思います。
藤原:いわゆるエンタメや2.5次元舞台の多くは大きな劇場で上演されますよね。そこでは、お客さんに向けて何かを発信する。でも、キャパが30などの小劇場で同じ芝居をすると不自然になってしまいます。
お客さんにこう見せたい、こういうものを届けたいというよりは、今、目の前にいる相手とセリフを交わして感情を交換した結果、生まれたものを観てもらう。舞台上の相手とのやり取りだけで満たされる空間を、お客さんに感じてもらう。
――とてもぜいたくな空間のように感じます。
藤原:役者は演技プランを考えて舞台に立つものなんですけれど、そんなものがぶっ飛ぶようなものを投げられて、自然と体が動いて、自然とセリフが出て、その役とシンクロできたような気がする瞬間が一番楽しいです。とても難しいんですけれども、どうやろうかという狙いが関係なくなるんですよね。
さっき拓海が言っていた、前回の公演で大和にとんでもないものを投げられて必死に受けた…それこそが純粋な芝居なんじゃないかなと思います。
東:あの時は陪審員長として、大和さんを止めなくちゃいけないと心の底から本気で思いました。もし僕が止められなかったとしたら本当に手を出していたんじゃないかと思ってしまったほどでした。

藤原:色々な舞台を経験するうちに、色々なことが分かってきました。自分が心から好きじゃないことや、やらなきゃと思ってやったことって、お客さんに好きになってもらえないんですよね。
扉座の有馬自由さんが、「自分が客席で見ていて気持ちいい芝居をやりたい」とおっしゃっていたんです。良い言葉だなと思いました。自分の感性が100パーセント正しいとは思わないけれど、僕も、自分が客席で観ていたとしたら、「この人の芝居は心地いいな、気持ちいいな」と思えるような芝居をしたいと思うようになりました。
若い頃は、自分が自分が、という気持ちもありましたが、それだとうまくいかないことも多くありました。今の拓海と同じ24歳の頃なんて、「このシーンでうまく持っていくためにはどうすれば?」なんて、そんなことばかり考えていました(笑)。
――東さんは若いのにとても落ち着いていますね。
藤原:しっかりしていますよね。初めて共演した時、拓海はまだ21歳だったのに、女性役に物怖じすることもなく、板の上でその役を100パーセント全うしようとしていました。頼もしかったですね。ヒロイン役なんて渡されたら、若い子だったらおたおたしちゃうと思うのに。
東:おたおたしていますよ!(笑)
藤原:だとしたら、それを見せないというのが強いと思うよ!(笑)

――最後に、本作をより楽しむためのコツと、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
東:話のベースは、「少年が本当に事件を起こしたのか?」ということです。話が進んでいくうちに、12人それぞれの感情の揺れや生い立ちの話でストーリーが動いたりずれていったりもしますが、ベースは動きません。
観ながら「この人の考え方、嫌い」とか思ってもいいです(笑)。でも、その「少年が本当に事件を起こしたのか?」という主軸だけは忘れないでいただければと思います。
藤原:理想は、俺たちのことを全く知らない人が当日券で入ってきて、面白いと思ってもらえることです。自分のファンの方はもちろん、そうじゃない、全く知らない人も楽しんでもらえる舞台。
誰かが話を脱線させたら、誰かが2倍の力で引き戻します。役者である以上、思うままにやりたいというエゴは大事だと思うけれど、話の面白さの軸は外さないようにしたいです。ひとつの演劇をみんなで作り上げるので、皆さんはただただ、楽しんで観てもらえたらと思っています。
取材・文:広瀬有希/撮影:ケイヒカル
広告
広告