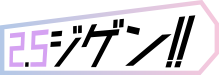5月22日(土)幕開の「ハンサム落語2021」で共演する西田シャトナーと平野良。演出家と出演者として数多くの作品を上演してきた2人だが、ともに演者として同じ舞台に立つのは、今回初となる。
2.5ジゲン!!では、2人に対談取材を実施。前半と後半に分けてインタビューをお届けする。前半となる今回は、2人の出会いや第一印象、お互いの演劇観などについて話を聞いた。
お互いの第一印象と思い出
――お二人はこれまで数多くの舞台を一緒に作られています。お互いの第一印象は覚えていますか?
西田シャトナー(以下、西田):僕は覚えています。平野くんが「人見知りなんですけど頑張ります」と言っているのを聞いて「徐々に調子を上げていくタイプなんだろうな」と思いました。
その後、しばらく稽古をしていて驚きました。平野くんには僕の頭の中にあることが全部伝わるんです。「先輩のボケをうまく回収してくれ」のような無茶振りもね(笑)。
僕は劇団時代、ずっと気心の知れた仲間たちとばかりやってきたので、外部の俳優さんに演出オーダーを伝える技術が身についておらず、劇団時代以降「自分の考えがなかなか伝わらない」「自分の演出案が駄目なのかもしれない」というジレンマを抱えて、10年ほど過ごしていました。だから、平野くんには驚いたとともに、自分の演出案そのものは間違いでなかったんだと救われた気持ちになりました。
そんな風に、最初から意思疎通ができたものですから「人見知りする」っていうのはネタ振りだったのかな? とさえ思ったのですが、後で彼の役者仲間たちから「平野くん、人見知りしますよ」と聞いたので、これは幸運な出会いだったのだなと改めて思いました。
平野くんは、クリエイターとしての想像力の領域が深いんです。僕は演出家として、俳優さんたちにとってだいぶ厳しいラインのパントマイムなどを要求するんですが、彼はすぐにピンときて僕のオーダーに応えてくれる。イマジネーションの力が強く、俳優としての活動だけでは物足りないのでは? と思ってしまうほどです。それは、もともと持っている彼の想像力の深さに加えて、読書量によるものなのではないかと感じています。

――平野さんは、西田さんと知り合った頃を振り返っていかがですか。
平野良(以下、平野):僕はずっと映像のお仕事をしていて、舞台のお仕事を始めたのは2008年からです。羽原大介さんの「ラフカット2008〜愛のメモリー」という作品が初舞台でした。
そこで感じたのは「舞台の世界、えぐい!」でした。つかこうへいさんの流れなので、台本は一応あるけれど、稽古が“口立て”なんです。稽古場で言われたことをその場で台本に書かない。舞台ってこういうところなんだ…と衝撃を覚えました。
次に出演したミュージカル『テニスの王子様』では、ものすごく多くのお客さまの前でお芝居をして、黄色い声援を浴びて…。原作のキャラクターがある舞台だったので、公演中にも「そのキャラはもっとこうです!」って言う意見を頂いたり、すね毛の剃り忘れを怒られたり(笑)、一挙手一投足見られていることを実感しました。
それを経て西田さんの舞台に初めて出させていただいたのですが、がむしゃらに活動していた時期でしたね。

西田:それはすごくいい経路だね。口立ては演劇の原型で、元々、文字のない時代には台本はなく作られていたものだから。そうやっていくうちに「台本あった方が良くない?」っていうことで書き始められたようなものだし。
それから、お客さんの意見ね。昔はそうだったから。怒られるというより“一緒に作っていく”という感覚かな。お客さんが「もっとこうした方がいい」とどんどん言ってくれていたのが、時代を経るごとに作る側と観る側に分かれていってしまった。
「テニミュ」は、いい意味で原初演劇に引き戻してくれた作品だなと思っているのね。遠慮なく「すね毛剃ってない!」って、そんなん普通は言うてくれへんから(笑)。すね毛が生えていたとしても、お客さんが「そういう作品解釈なのか」っていうふうに観る時代が長く続いていたからね。
平野:シャトナーさんとの出会いで、いろんな経験を一気にさせてもらいました。舞台とは何ぞや? 人に見られるとは何ぞや? というようなことも。舞台の広がりや無限性を教えてくれました。
――西田さんは、平野さんとの印象的なエピソードはありますか?
西田:自分でも「こんなオーダー通るかなぁ」と思っていたシーンがあったんですけど、彼は「こうですか」なんて言いながら、いきなりワンテイク目でできてしまって(笑)。その痛快さでめちゃくちゃ面白くて、笑ってしまったのを覚えています。
劇団時代に何年かかけて到達したやりとりに、一回で辿りついてしまったんです。その舞台には劇団時代のメンバーである保村大和くんも出てくれていたんですが、彼も「あいつすごいな」ってびっくりしていました。
それから何年かして彼が主演の舞台を作ることになった時は、思う存分、演出のオーダーを出せて本当に面白かったです。

――平野さんならできるだろうと思い切ったオーダーをしてしまうことはありますか。
西田:ありますね。演劇をするからには、実験・冒険の領域のことをやりたいんです。できるかどうか分からないことを試すことができる。そういう楽しさがあります。僕にとって、彼がいることで未知の領域に進むことができる。
――平野さんは、西田さんからのオーダーで印象に残っていることは何ですか。
平野:5人芝居のときのことかな。2015年の「ムッシュモウソワール」。雑談で「これ面白いよね」と話していたことをそのまま舞台に持ち込むんです。無理なオーダーという感覚ではなかったですね。
――オーダーに応えるというより、お互いの感覚が似ているという印象でしょうか。
西田:ひょっとしたら“オーダー”じゃなかったかもしれない。これができたらすごいけれどどうしようかという話をしていたら「できる」と。じゃあ、オーダーさせてもらいますと(笑)。
平野:あの時は、休憩に入ったらお茶会みたいな感じでしたね。稽古が全然始まらない。でも、そのお茶会がすごく重要だったんですよね。
西田:そうそうお茶会。「このシーン、全員ウエーイしか言わんことにしよ」って話していて、やってみたらめちゃくちゃ面白かったり(笑)。まさか本当にやるとは思わないで喋っていたことが採用されるのは面白さがありますね。
芝居とは、演劇とは…
――西田さんは演出家として、平野良さんの力をどう見ていますか?
西田:僕は、演劇というものがどう立ち上がってきたのか? ということを追体験したいんです。我々は太古からずっと同じことをしているはず。僕たちは一体、何をしているのか…それを知りたいんです。近代化する前の時代のことをやりたいんです。良くんと芝居を作る作業をしていると、今の演劇づくりのシステムや枠が解かれていくように感じます。
演出家が俳優にするオーダーは明確で疑問のないものであり、そして俳優はそれに的確に応えていく――。ある種、プロフェッショナルなものづくりであり正常とも言えますが、あまりにも現代的過ぎて、演劇の本質から外れているのではないかと思うところがあります。
良くんが板の上に立ち、僕は板の外から見ているんだけれども、ものづくりは一緒にしている。一緒にパーツを持ち寄ってはめていく、みたいな感覚があります。バンドでいうところの3ピースバンドのような。誰かが曲を作って、誰かが弾いて、と決めているのではなく混然としながら進んでいく。彼のおかげで、僕が作りたい芝居が作れている。いい芝居を作らせてくれる。そういう恩を感じています。
例えば先ほど出た「ムッシュモウソワール」。1作目は5人が主役だったけれども、2作目は良くんが主人公で、彼じゃなかったら作れなかった原初演劇になりました。

――平野さんにとって、西田さんはどういう存在ですか。
平野:僕の心の中には3人の演出家さんがいて、その中の一人がシャトナーさんです。
僕は物心ついたときからお芝居をやりたくて、中学生からお芝居を始めて。でも一回は辞めて社会人になった時、ぐるぐると考えてしまったんです…。お芝居って何なんだろう、何でやりたいんだろうなって。お芝居で食えない時期にもずっと考えていました。
そうしているうちに、お芝居をしたいんだけれど、どこかで思想家でありたいと思うようになりました。人を演じるのだけれども、自分のアイデンティティや自分たる所以といったものを考えてしまう。
“シャトナー語録”で、胸に刺さって、ずっと取っておいている言葉があって、気付いたら僕が初めて演出した舞台「BIRTHDAY」(2019年)の現場でそれを言っていました。
――どのような言葉だったのでしょうか。
平野:「一歩踏み出すか、踏み出さざるかを考える」です。普通に歩いているけれど、その一歩を踏むかどうかを、その刹那までどこかで考えているんだと。それを以前聞いて、確かにそうだなと思ったんです。
自由意志の有無について科学的な考え方があるけれど、自由意志があると想定しても、「その一瞬まで分からない」と思いました。シュレーディンガーの猫じゃないけれど、一瞬先のことは何も分からない。なのになぜ歩けているのか。歩くという事象さえ細分化できるんですよね。
それから「山小屋で一人で踊っていても演劇として成立する」。自分自身も観客であるということです。平野啓一郎さんがおっしゃっている“分人”の考えを先取りしているように感じています。
分人は、色んな自分がいていいじゃないかという考え方です。この現場ではこういう僕、ここではこういう僕、と分けて考えていい。主観で見ている自分もいるし、客観で見ている自分もいる。
後輩たちに「役者として大切なことは何ですか?」ってよく聞かれるんですけど、自分ですらお客さんだと思った方がいいと常に思っています。スタッフさんや共演者もお客さんだと思って、その人たちを感動させるのが最初。自分が感動して、その感動の距離を伸ばしていく。そういうのも全部、シャトナーさんの言葉からどんどん芽吹いていったんですよね。
西田:僕の言葉から良くんが学んだんじゃなくて、きっともともと良くんの中にあった感覚なんでしょうね。聞いたから分かるという類のことではなく、もともと分かっていたから分かる。
情報ってきっとそういうことなんじゃないかな。例えば、良くんが言ったことが僕の心に音波として届くんじゃなくて、同じ振動が頭の中で起こったから伝わったことになる。頭の中の世界のことだけれどね。

* * *
インタビュー前半では、それぞれの印象や演劇観などが語られた。互いに刺激を与え合う2人が今回、舞台上で初共演を果たす。後半では「ハンサム落語」の魅力や捉え方、落語にまつわるエピソードなどについても聞いていく。
文:広瀬有希/写真:ケイヒカル
広告
広告