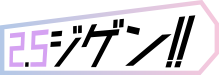幻想的な世界観を紡ぐ語り部と、参加者と呼ばれる受け手とが、想像力でつながる劇団おぼんろ第21回本公演『瓶詰めの海は寝室でリュズタンの夢をうたった』が、8月18日(木)〜8月28日(日)に東京・Mixalive TOKYO Theater Mixaにて上演される。
同演目は2021年夏に上演され、大きな話題となった風変わりな冒険譚。反響を受けて、2022年8月には児童書として書籍化される。また、2022年版の舞台では新たなキャストを迎えてのWキャスト&シャッフルキャスト体制に。捲り子という新要素も加わり、スケールアップした作品となりそうだ。
2.5ジゲン!!では劇団主宰であり脚本・演出を一手に担う末原拓馬へのインタビューを実施。稽古場レポートとあわせて、末原の本作へ懸ける思いを聞いた。

稽古場レポート
稽古場にはフランクな雰囲気が漂い、演出家・演者の境目なく会話に花が咲く。末原、ひいては劇団おぼんろのアットホームな空気感が、そのまま反映されているのだろう。稽古中盤ということもあってか、今回から出演となる新キャスト勢も劇団の一部に感じられるほど馴染んでおり、すでに1つのカンパニー感が生まれていた。
セットや小道具はまだない状態の中、語り部であるキャスト陣たちの想像力が積み重なり、少しずつ世界観の輪郭ができていく。印象的だったのは、末原が「こういう感じの絵にしたい」と発信すると、すぐさま周りから「こういうのは?」と案が飛び出してきたことだ。

末原が「陽」と評する橋本真一は、積極的に動いて次々と提案をしていく。対照的に日向野祥は鋭い視線で黙々と取り組んでいた。大久保桜子は途中から裸足になって、周りに負けじと気合を入れていた。劇団員のわかばやしめぐみと塩崎こうせいを軸に芝居が始まれば、たちまちそこには海の中の世界が姿を現す。

去年上演している演目とはいえ、今年は捲り子が加わり表現の幅もより広がるのだろう。新たに増えた選択肢の中の、どれとどれを組み合わせてみようかと、真剣な眼差しの中にも、どこか子供のようなワクワクした表情を見せる末原の表情が印象に残っている。

ネタバレに直結するシーンのため具体的には言及しないが、稽古場にはたった5人のものとは思えないほどの熱が、短時間の間に凝縮されていた。希望と絶望の先に、老人と少年は果たして何を見つけるのか。作品のほんの一端に触れただけでも、この冒険を見逃したらもったいないというワクワクした気持ちを残してくれた。

今回の稽古場レポートでは、残念ながらその芝居を観られなかった語り部もいる。彼らが加わり、さらにシャッフルキャストによって組み合わせが変わる度、この冒険譚は違った表情を見せてくれることだろう。
末原拓馬インタビュー
――今年はWキャスト・ミックスキャストという新たな要素を取り入れての上演となります。新たな形での上演について、稽古の中で手応えは感じていますか。
去年は自分が精神的にギリギリなまま書いて、そのまま稽古、本番へ…という形で、すごく自分の気持ちのままに作っていった作品でした。当時父が亡くなって、その父のことがあって書いた作品だったから、自分も劇団員もそのことへの思いがすごく乗った状態だったの。
だけど今年は、そこから1年経って、この演目を世界中で命を持った物語にしようと動き出していて。Wキャストもその動きの1つで、今はまず物語の核の部分を共有することに重きを置いて稽古しています。なるべく速くゴールにたどり着くようにっていう作り方ももちろんあるんだけど、今回はそうではなくて、語り部としてただ演じるだけの芝居に留まらず“語って”ほしくて。
物語は僕が書いてはいるけど、参加(観劇)してくれた皆の物語にならなくちゃいけないと思うし、それは演者に関してもそうで、自分の人生にいったん落とし込んだほうがいいなって。そこが同じ役を別の人がやるっていう上ですごく難しいんだけどさ。でも差を出そうと奇をてらった芝居をしなくても、その人は生きてきただけで、その人だけが持つものがあるわけじゃないですか。だから僕はそっちと役を馴染ませてほしいなって、皆とたくさん話している段階ですね。

――役を深める過程で、同じ役を演じる橋本真一さんとの価値観の違いは感じますか。
価値観もだし、肌の色の違いを感じています。並ぶと差がすごくて、よく2人で笑っているんだけど(笑)。根本的には似ているところはあるなと思っていて。彼は去年、配信で観てくれていて、その後初めて喋ったんだけど、そこで真一もお父さんを早くに亡くしているっていう話をしてくれて。そこで遺された者としてどう生きていくか、みたいなこととか、女性家系で育ってきたこととか、そういう質が近いっていうのはあると思う。
違いで言えば、彼は陽の部分のエネルギーがすごく強い。色で言えば暖色で。僕はどちらかというと冷たい方への感受性が強くて、寒色だと思う。去年も演じている間に体重が7~8kg減って、立っているのがやっとっていう状態でやったんですよ。結果的に、儚くて死の匂いがするような役になったんですが、真一は陽のエネルギーがほとばしる感じがすごく素敵だなって。
この1年間、書籍化するにあたって役と自分は切り離して書く作業をしたんだけど、そこでクラゲに関して「飛び跳ねるように」とか「弾けるように」っていう描写を入れていて。だからそのクラゲの概念にすごく真一は合っていると思います。
――末原さんが演じるクラゲも、この1年を経たことで去年とはまた違う受け取り方ができる役になっていそうですね。
なっていると思います。去年は父のこともあって、どこか儀式的な意味もあったし、やっぱり「死ぬまで生きろ」ってことをすごく感じていたんですね。だけど今年は、そこからもう一歩普遍的な登場人物として(クラゲを)立ち上げたいなって思っています。僕は劇団では語り部としてやっていて、自分として語るっていうことをすごく大事にしたい。去年の自分と今年の自分は違うコンディションだからこそ、今年はどういう意味でこの物語を語りたいんだろうっていうのを、ここから見つけていきたいですね。
――今回、作家デビューとなりますが、本として表現するという作業はいかがでしたか。
自分がいないところでも物語が続いていくんだっていうことがすごく嬉しいです。ただ、児童書として出すということで、舞台版とは話の筋も変えているんですよ。表現の部分でも、怖くならないように、子供が読めるようにって。文章はずっと書いてきたけど、そのへんがめちゃくちゃ難しかった! 僕を知ってくれている人は、末原拓馬が書いた文章として補完してくれる部分があると思うんですよ。でもそれも一旦ゼロにしなきゃいけないし、本になることで誰がどこでどんな風に読むかも分からない。だからこそ、より語り部と参加者の関係が顕著で、本を読んでくれた人のそれぞれの物語が世界中で紡がれていくようにっていうのを考えましたね。あとはやっぱり、舞台上で音や照明で表現したものを「どう書くの?」みたいなことはよくありました(笑)。
――それはもどかしそうですね。
すごくもどかしかった! 舞台上では5人が並べば、5人の姿が目に入るじゃない。だけど、本では視点も絞らなきゃいけないので、トノキヨとクラゲに集約したり、そのぶん過去のことを掘り下げたり。生きるというメッセージ性についても、より磨き上げられたと思うから、できれば舞台に参加する人にも本を読んでもらいたいですね。
ゆくゆくは世界中でこの演目を演じる語り部が増えたらいいなと思っているんです。演じなくても、参加者が家に帰って語り部になってくれたら嬉しいし、それが世界を変えることにつながると思っていて。来年以降も上演して、その規模を広げていって、本を読んでくれた子供が自分で舞台に行ける年齢になった頃にも上演している状態に持っていけたらいいな〜と思っているんです。
――舞台の上演期間以外も、書籍として思いが伝播していくというのは夢がありますね。
そうなの。演劇って物語の寿命がどうしても短くて、それがすごく昔から悲しいなって思っていた部分でもあって。でもそれが書籍と一緒に広がっていってくれると思うと嬉しいですね。
――今年はどんな冒険が観られるのか楽しみです。最後にファンへのメッセージをお願いします。
気軽に観にきてくださいって、これまでやってきたんですよね。それはもちろん変わらないんですけど、そうじゃないのかもという気持ちも芽生えていて。すごく特別なこととして劇場に来るのもいいんだな、って思うようになりました。
夏休みを振り返ったときに、ポイントで思い出すことってあるじゃないですか。「リュズタン」に参加した日が、そういう夏休みのすごく特別な1日として残ってくれたらいいなって思うんです。大事なのは物語自体よりも、それを受け取って胸の中に「リュズタン」の物語を宿した“参加者のあなた”が、次の日からどんな物語を過ごしていくのか、だから。自分の物語を紡ぎにくるつもりで、来てくれたら嬉しいよねって思っています。

***
柔らかながらも、一つひとつの言葉から「リュズタン」へ懸ける思いが汲み取れるインタビューとなった。稽古場で物語の一端を垣間見たが、劇団おぼんろの真骨頂はやはり幻想的な空間に浸ってこそだろう。稽古場でも面白そうなアイデアが飛び交っていただけに、実際の劇場でどんな物語に“参加”できるのか、期待は高まるばかりだ。
取材・文:双海しお
広告
広告