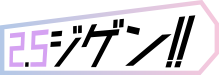舞台「ヨルハ」シリーズや舞台「トワツガイ」、音楽劇「ジェイド・バイン」など数々の2.5次元舞台で衣装や特殊造形を手掛けている早瀬昭二さん(マッシュトラント)。担当するものは舞台に限らず、アーティストやアイドルのステージ衣装、テーマパーク衣装など、その活躍は多岐にわたる。頭の中にある夢がそのまま現実の形となったような衣装や小道具の数々は、観る者の心をワクワクさせ続けてきた。
今回2.5ジゲン!!では、早瀬昭二さん(マッシュトラント)にロングインタビューを実施。前編では、物づくりのルーツや、仕事をする上で大事にしていることなどをたっぷり語ってもらった。
――まず、造形・衣装の製作を始められた経緯についてうかがっていきます。ものづくりのきっかけは何だったのでしょうか。
幼少期、体が弱くて「10歳まで生きられないんじゃないか」と言われていたんです。幼稚園や小学校にはほぼ行かず、毎日家でお絵かきをしたり、粘土やアルミホイルでアニメに出てくる乗り物やロボットなどを作ったりしていました。結局はその後もなんとか生きていくんですけれども(笑)。
周りの子どもたちと同じように仮面ライダーやウルトラマンが好きだったのですが、それらの衣装や顔を“どのように作ったらいいのか”をいつも考えていましたね。方眼用紙でお面を作ったりして。
そんな中、小学生のときにガンプラ(「機動戦士ガンダム」シリーズのプラモデル)ブームが起こって「HOW TO BUILD GUNDAM」(ホビージャパン)という本が発売されました。模型製作の先輩方による、市販のガンプラ改造・カスタマイズの手引き本です。
ガンプラに限らずですが、当時はまだアニメで見る画と実際に販売されるおもちゃの造形には差がありました。でも、「HOW TO BUILD GUNDAM」を読んで「自分でアニメと同じものが作れるんだ」と楽しさに気づいてしまったんです。市販のものをカスタマイズするだけではなく、すべて自分で作り上げる「フルスクラッチ」という手法があるのも知って「これは自分にもできるかも!」と、試行錯誤しながら作ってみていました。

(C)舞台 トワツガイ製作委員会 (C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
――幼少期から、市販のおもちゃを買って満足するのではなく、カスタマイズしたり自分で作る方へ考えが行っていたのですね。
針金とパテなどを使って「ウイングマン」のフィギュアを自分で作ったこともありました。目で見たものを形として出力したい、と思っていたんです。
造形を専門的に学ぶ高校に入学してからは、いわゆる“教科”の勉強ではなく、デッサンや水彩画、彫刻などを学びました。今のようにテクノロジーがまだ発展していなかったので、いかに「手で作るか」のノウハウを叩きこまれて。
――「洋服作り」に携わるのはその後でしょうか?
高校を卒業してからです。洋服作りに興味がわいて入学した服飾の専門学校では「同じ“作る”でもまったく違う」と感じました。これまでやってきた粘土や彫刻などが、盛り上げたり削り出して作り出すのに対して、洋服は平たい布を形にしていきます。でも、布だけでは球体は作れない…それが嫌で、「じゃあ、これまでやってきたこと(物作りと洋服作り)を混ぜてみたらどうだろう?」と思いついて。
でもこれは、僕が新しく思いついた考えではありません。1990年代に活躍したデザイナー、ティエリー・ミュグレーは、洋服の概念を覆すようなものを作っていました。バイクのハンドルであってもファッションとして見せるものにしてしまう。
「洋服は布で作るもの」というのは、誰かが作った概念なのかもしれない。「街で着られるものは洋服」「街で着ないような特別なものは衣装」と自分の中で線引きをして、どちらを作りたいのか自問してみたんです。
――そして“衣装”作りを選ばれたのですね。
楽しんでできるだろうなと思って。しかしその後の20代は大変でした。あまり大きい声では言えないのですが少々借金をしまして(笑)。返済するために、昼夜アルバイトをかけもちして働きました。服やアクセサリーを買う余裕もなかったので、余った布でブルゾンを作ったり、もらった鶏の骨を煮込んで乾かしてネックレスを作ったり(この日も身に付けていたもの)。「無いものは自分で作る!」「使えるものは何でも使う!」でした。

30歳までに何とか借金を完済して「ずいぶん経験値が上がったな」と感じました。経験した職種は30以上。その中には建築、塗装・ペンキなどの、“物作り”に役立つものも含まれていました。この技術と経験は活かせると思い、30歳のときに独立して仕事を始めて今に至ります。会社設立当初は、テーマパーク関連の業務をメインでやっていましたね。
原作付きの2.5次元舞台衣装の制作を手掛け始めたのは、西川貴教さんが総合プロデュースをしている「B-PROJECT」の舞台がきっかけでした。
――では実際のお仕事の流れと、特に意識していることや大事にしていることを教えてください。
すべてをお任せいただけるケース、1キャラのみご依頼いただくケース、などさまざまですが、自分のフィルターを通して理解するために、アイデアは必ず1度絵に描き起こします。自分で絵に描けないものは作れないので。デザイナーさんからいただく絵は「デザイン」であり、実際に人に着せるイメージとは異なります。
そのため、頭の中で想像した上で絵に起こして、人に着せた状態ではどうなるのかバランスを見ます。装飾の大きさがアンバランスではないか? 丸い部分はふわっと柔らかいのか? 風船のようにパンパンになっているのか? とか。
ファスナーやボタンの位置も、イラストでデザインとして成立していても実際の服として考えたら成立しないこともあります。それを修正するべきなのか、デザインとしてそのまま活かして作るのか、先方に確認するためにも絵に起こしてみるのが必要なんです。

(C)MAGES./STAGE B-PROJECT
原作の有無に関わらず、人物や世界観などの背景情報もヒアリングします。例えば、人間なのかアンドロイドなのか。アンドロイドであれば、作られてどのくらい経過しているのか、戦場で戦い続けているのか、メンテナンスはされているのか…。知りたいことをどんどん聞いて詰めていって、着るものはこの世界の織物工場で作られているのかな? なども想像します。
衣装の外見上の“情報量”を精査するのも大事です。例えば近年の作品は、セーラー服に肩当てをつけて背中には羽、バズーカをかついで…など、どんどん情報が盛り込まれてきています。装飾も細かいですしね。
しかし、たくさんのキャラクターがいる場合は、大事な部分はもちろん緻密にしつつも全員を豪華に作りこまず、グラデーションのようなイメージになるようにしたいんです。全員が情報量いっぱいの衣装を身につけていたら、観ているお客さんは目と頭の処理が追いつくだろうか? と考えてしまって。
――確かに、特に「ヨルハ」シリーズや「ヴィジュライ」(VISUAL PRISON 1st GIG/2022年)の衣装は、装飾がたくさん付いているのにシンプルさを感じます。
シンプルな情報で内容を濃く見せたいんです。一見凝っていそうだけれども良い意味で力を抜くところは抜いていたり、逆に、シンプルに見えるけれどもこだわりを持って緻密に作り込んだりもしています。

© 2017-2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
でも、舞台を観ているときは衣装はさらっと見てほしいと思っています。舞台の世界に浸ってほしいので、「あの衣装、一生懸命作ってる」と気にされたくないんです。「衣装よかったな」と思い返してもらえるのであれば、後で写真や映像で見かえしてもらえたら。
公演が終わってからSNSで制作過程や衣装の写真をアップで載せているものもあるのですが、それを見て「こうなっていたんだ!」と思ってもらえたらうれしいですね。作品を2度も3度も楽しめることになりますし。今は6月から上演される舞台「トワツガイ」の衣装・特殊造形を手掛けています。
***
話を聞いていて、彼の幼いころからの物づくりへの探求心と、学生時代や20代の頃のさまざまな経験が今の技術に生きているように感じられた。後編では、さらに詳しく各作品についてや、今後の展望、この仕事・業界を目指している方へのアドバイスなどを聞いていく。※28日(金)公開予定
取材・文:広瀬有希
広告
広告