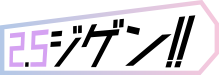2022年1〜2月にかけて上演されたミュージカル『ヴェラキッカ』のBlu-ray初回限定豪華版、Blu-ray通常版、DVD通常版が9月21日に同時発売されることになった。
TRUMPシリーズは、劇作家・末満健一がライフワークに掲げ2009年より展開する演劇シリーズ作品。劇伴を中心に活動する作曲家・編曲家の和田俊輔は、このプロジェクトに2012年より楽曲を提供し続けている。
2.5ジゲン!!では、今作の作・演出を手掛けた末満、音楽を手掛けた和田に対談取材を実施。『ヴェラキッカ』およびTRUMPシリーズへの思いや、10年来タッグを組んで仕事をしてきた互いの印象などをたっぷりと聞いた。
「観客は優秀なキャッチャー。想定以上に受け止めてくれる」

――ミュージカル 『ヴェラキッカ』Blu-rayおよびDVDの発売、おめでとうございます。上演から時間を経た今、作品に対してどんな思いがありますか?
末満健一(以下、末満):まずは何より、ファンの方々に感謝を伝えたいです。
『TRUMP』初演から13年、当初はシリーズをこんなに長く続けられるとは思ってもみませんでした。これも支えてくださっているお客さんのおかげ。ファンあってのエンターテインメントだと、ひしひしと感じています。
原作のないオリジナルの演劇作品は、Blu-rayやDVDとして残らない場合も多いもの。こうして形に残していただける上、初回限定豪華版まで出していただけるというのは、本当にすごいことだと思います。作り手としては夢物語のようで、まだ現実感がないです。
和田俊輔(以下、和田):本当に感慨深いですね。仮編集された『ヴェラキッカ』の公演映像を見ながら「こうやっていつでも見返せるのはやっぱりいいなあ」と感じました。
ちなみにその映像は、末満さんがスイッチングした配信映像。仮タイトルは「スエッチング」になっていましたよ。
末満:スタッフさん、遊んでるなあ(笑)。

和田:で、映像を見返していて思ったんですが、やっぱり作っている最中には分からないことが、今改めて見えてきたりしますね。観客の皆さんもそうでしょうけれど、作り手としても時間が経って見返してようやく分かることがあります。
末満:作っている最中はどうしても、自分の至らない点ばかりが気になってしまうからね。「ここをもっと良くできるんじゃないか」とか。
僕も先日、監修のために映像を見たときにようやく「これ面白いなあ」と思えました。手前味噌な自慢をしたいわけではなくて、作品から時間と距離を置いてみて初めて見えることって、やっぱりあるんです。
和田:渦中にいると分からないことって、案外多いかもしれないですね。
末満:『ヴェラキッカ』はありがたいことに初日から千秋楽までずっとスタンディングオベーションをいただけたんですが、当時の僕は自分の至らない部分ばかりが気になっていました。もちろんスタンディングオベーションはものすごく嬉しいのですが、実感として「どうしてこんなに喜んでくれるんだろう?」と不思議な気持ちの方が大きくて。
でも今になって作品を見返すと、良いところが見えてくる。それでようやく「ああ、お客さんもこういうところを受け止めてくれていたのかな」と納得できました。
和田:演劇作品を観に来るお客さまって、キャッチャーとして優秀ですよね。「どんな球でも逸らさないぞ!」という気概を感じる。
末満:すごいよね。こちらが想定している以上のことをきちんと受け止め、感じ取ってくれている。「演劇を最後に完成させるのは観客である」とはよく言われますが、本当にそのとおりだなと感じています。
「あえてキレイにはまらないピースを置いた」
――『ヴェラキッカ』の反響として、印象的なものは?
和田:上演後ではなく稽古中のキャストさんからの反応ですが、僕にとって印象的なエピソードがあります。
二幕で披露される『幻想幻愛メランコリック』(S18)を稽古場で初めて流したとき、愛加あゆさん(ジョー・ヴェラキッカ役)が「これぞTRUMP、末満さんと和田さんペアのつくる曲だ!」というツイートをしてくださいました。
そのツイートを見て、僕はとても嬉しかった。
TRUMPシリーズにおいて『ヴェラキッカ』はやや異色に見える存在で、キャスト陣も最初はこの作品をどう捉えて演じたらいいか迷っていたのかもしれません。でも、『幻想幻愛メランコリック』という曲を通して「ああ、これもしっかりTRUMPなんだ」ということが伝わったのかなと。
僕ら二人が『ヴェラキッカ』でやろうとしていることが、キャストの皆さんに明確に伝わったんだと実感できた。この曲を書いてよかった、と思えました。
末満:『幻想幻愛メランコリック』と『愛は毒だ -Liebe ist Gift-』の2曲については、作品全体の中でもちょっと特殊な曲と言えます。
というのも、この2曲は作品の構造にキレイにはめ込むことができない、パズルに例えると余計なピースのような曲なんです。極端な話、ストーリーラインだけで考えるとこれらは「不要な曲」とさえ言える。でも、はまらないピースをぽんと置くことによって、作品が拡張される効果を狙いました。

――受け止める側の違和感を、あえて掻き立てたのですね。
末満:今作は、どうしても「体(てい)の良い形」に仕上げたくなかったんです。お行儀良くキレイに構成されたミュージカルではなく、どこか歪なものにしたいという思いがありました。
直線上にいる人にまっすぐ届くだけではなく、ストーリーラインという幹から大きく広がった枝葉が、あらぬ方向から観客にリーチする。そんな物語にしたかったんです。
『ヴェラキッカ』という脚本の真の構造は、まず偽りの主題歌から始まって、1時間40分プロローグが展開され、そこでようやく真の主題歌が鳴る……というもの。つまりこの作品には、ウソの主題歌と本当の主題歌が存在するんですね。
それはもちろん観客には知らされていなかったわけですが、肌感覚としてきちんと受け取ってくれたお客さんが多かった。「なんだかよく分からないけど、とにかくどえらいものを見た」という反響が多く、ありがたかったです。
和田:『愛は毒だ -Liebe ist Gift-』は、とくにお客さまからの反響が大きかったですね。
末満:あれは、曲の持つ力がすごかったんだよ。ぴったりはまらない違和感を音楽の力で押し切った曲だった。

――TRUMPシリーズはストレートプレイからミュージカルまで幅広いスタイルで上演されていますが、『ヴェラキッカ』をミュージカル形式で上演したのは何故ですか?
末満:僕は、歌には感情や表現を拡張させる力があると考えています。ですから、歌で何かを拡張させる必要のない物語はストレートプレイで上演します。
『ヴェラキッカ』に関しては、題材的に歌が必要だと感じたのでミュージカルにしました。
先程も話したとおり、ひとつの方向からまっすぐ届けるだけじゃなくて、観る人のいろいろなセンサーに多角的にアプローチしたかった。それでミュージカルという形を選択したんです。
――届けたかったものを、届けきった手応えはありますか?
末満:届けきったという手応えは、今までのどの作品においても無いんです。やっぱり毎回「もっとやれたな」「ここが足りなかったな」という部分が出てきます。
ただ『ヴェラキッカ』に関しては、予想していた以上にしっかり受け止めていただいたという実感がある。観客にとって釈然としない題材をあえて試みた作品なので、拒絶する人も少なくないんじゃないかと思っていたんです。
でも思いのほか多くの方に「良かった」と言っていただけて、皆さんのキャッチ能力の懐深さを改めて実感しました。
『火の鳥』『ブッダ』の影響と、末満自身の死生観

――TRUMPシリーズというプロジェクト始動時から比べ、心境に何か変化はありますか?
末満:自分の中では、とくに大きな変化は感じていません。物語をどう完結させるかという道筋もすでに決まっています。
……なんて言うと、まるでJ・K・ローリングさんの逸話みたいですけれども(笑)。実際にラストシーンはセリフまで決めてあるんです。まあ、いざ書いてみたら変わる可能性もありますが。
――シリーズを始めるきっかけとなった「自身の死生観を表現したい」という思いは、今も?
末満:はい、変わらないですね。
僕は以前、手塚治虫さんの漫画『火の鳥』にはまり込んだ時期があって、そこから顧みた自分の死生観がTRUMPシリーズに大きく反映されています。あの壮大な世界観をひとりの人間が生み出したというのは、じつに驚きですよね。
手塚先生はあの作品をライフワークだとおっしゃっていて、完結する前に亡くなった。僕は勝手にそこを追っかけているというか、「この死生観の再構築を、自分は死ぬまでにやり遂げてみたい」という思いを持って取り組んでいます。そこに変化はありません。
和田:目標の部分は変わらなくても、死生観そのものは少しずつ変化していませんか? 僕から見ていると、末満さんの死生観はどんどん深まっているように思います。
末満:そう? 変化してるかな?
和田:『火の鳥』の話題で思い出しましたが、僕、末満さんを見ていると手塚先生の『ブッダ』という作品を思い出すんですよ。
末満:『ブッダ』もすごい作品だよね。

和田:『ブッダ』も『火の鳥』と同じく長編ですが、こちらは序盤・中盤・終盤と、物語が進むにつれてかなり雰囲気が変わっていくんですよ。それは描いている手塚先生の価値観がだんだん変わっていったからなのかなと想像しているんですが、それと同じ現象が末満さんにも起きている気がします。
末満さんのライフワークである以上、TRUMPシリーズには末満さんのライフ=人生や価値観がそのまま反映される。だから、根本にある死生観は揺るがなくても、そこから伸びる枝葉の部分には変化が起きているんじゃないかなと思っています。
――和田さんから見ると、末満さんの死生観や雰囲気がどこかしら変わってきていると。
和田:そう思います。うまく表現できないのですが、まず以前に比べていろいろな物事に対する諦念が膨れ上がってきている。そして、その先にある希望のようなものを「どうやって見つけようか」という模索の仕方も、結構変わってきている気がします。
末満:僕自身はとくに変わったつもりが無いんだけど、自分には分からないですしれないね。過去と現在の自分の死生観を比べることって、事実上不可能だから。客観的に見て初めて分かる部分なのかもしれません。
かつては小劇場のライバル同士。「今も牽制し合う仲」
――お二人が一緒にお仕事をするようになったきっかけは?
末満:和田さんとの初仕事は2009年だから、もう13年ほど前ですね。
和田:厳密に言えば、お互いの存在はもっと前から知ってたんですよね。ふたりとも関西の小劇場で活動していたから。
僕は「デス電所」という劇団で座付きの作曲家をしていて、末満さんは「ピースピット」という演劇プロジェクトの主宰としてプロデュースワークをしていた。お仕事としては、舞台版『千年女優』(2009年)で脚本・演出を任された末満さんが僕に声をかけてくださったのが最初です。
末満:名前と存在は知っていたけど、仕事として関わるのはそれが初めてでした。
和田:というか、あえて交わらないようにしていたかも。いけ好かないってわけじゃないけど(笑)。
末満:作風的に、自分とは全く違う作品を作っている劇団の人という印象があった。まあ当時の小劇場は、同業者が牽制し合っている空気感がむしろ健全だったんですよ。仲良しこよしじゃなくて、バチバチとライバル視し合ってるみたいな。
和田:そうそう。だから末満さんに声をかけられたときは「貴重な機会だし、やってみようかな」という気持ちで引き受けました。最初は異文化コミュニケーションみたいな感覚でしたね。

――末満さんは何故、和田さんにお声がけされたのですか?
末満:彼の関わった作品を観て「音楽がすごくいいなあ」と思っていたんです。オリジナル楽曲でこれだけのクオリティのものを全曲書き下ろしてもらえるのは、劇団として羨ましいなと。
そんな矢先に、『千年女優』のプロデューサーから「楽曲はフルスコアオリジナルで作りましょう」とお話をいただいて。それなら和田さんに頼んでみたい、という流れでお願いしました。
――今やすっかりツーカーの仲という印象があります!
和田:いや全然ツーカーじゃないですよ(笑)。今でも牽制し合ってます。
末満:仕事以外では会う機会もなかなか無いしね。とくにコロナ禍になってからは仕事関係の飲み会も無く、本当に現場でしか顔を合わせないです。
和田:でも末満さん、場当たりで劇場に集合して3日間くらい詰めた後、仕事を上がる前にスッと寄ってきて、なんでもない話をし始めるときがあるじゃないですか。僕、あれ結構嬉しいんですよね。
末満:近況報告するタイミングがそこしか無いんだよ(笑)
和田:確かに。でも、長丁場が終わってホッとしたタイミングで雑談を持ちかけてくるから、「なんだ喋りたかったんだな、かわいいとこあるやん」っていつも思うよ(笑)
――お互いに「ここは自分と似ているな」と感じる共通点はありますか?
和田:ストイックさ、かなあ。
僕自身がかなりストイックに仕事を進めるタイプと自覚しているんですが、末満さんも相当ストイック。というか、作品やアウトプットに対してあまりにもストイックなので、「そこまで徹底して貫くのか」とびっくりすることが多々あります。
たとえば「僕だったらここまでは頑張る」というラインがあったとして、末満さんはそれをさらに超えていく。作品というコップに注いだ水がもうとっくに溢れているのに、さらに「まだまだこんなものではない」と注ぎ続けるのが末満さんという人なんです。そこは共感というか、むしろ尊敬しています。
末満:僕は、和田さんと自分はある意味で真逆の人間だと思っています。性格面でも、クリエイターとしての向き合い方も、真逆の位置にいると思う。
世界との関わり方が全く異なるんですよ。僕自身は、内側に自分を閉じていくことで作るものを洗練させようとするタイプ。一方で和田さんは、自分を取り巻く世界を外へ外へと拡大していくことで作品性を押し広げていこうとしているように思えます。
和田:ああ、そうかもしれない。
末満:そういう意味で僕らのやり方は真逆だけれど、ふたりとも根本の部分にあるのは向上心なんです。上昇志向、野心というか。そこには強く共感するし、シンパシーを感じています。
その辺りは似ているといえば似ているのかな。同じ場所を真逆のやり方で目指す形になっているので、面白いなあと思いますね。
目指すのは、和製ミュージカルで「会心の一本」

――『ヴェラキッカ』もそうですが、海外作品の翻訳ではなく、オリジナルミュージカル作品を作る上での苦労や楽しさはありますか?
和田:オリジナルの旋律で日本語の曲を作る作業は、やっぱりとても楽しいです。日本語独特の語感を活かせますから。
末満:輸入ミュージカルには、原曲と脚本が絶対のものとして存在しています。このため、日本で上演する場合には「原曲のメロディ」に「翻訳した歌詞」を強引にでも乗せていくという作業が必要になります。
原曲のメロディは日本語のために作られたものではないし、脚本の意図を汲みながら翻訳した歌詞も、そのメロディのためだけに書かれた言葉ではありません。だから、このやり方で日本語の語感を活かしきることは非常に難しいんです。
日本語の醸し出す音感、語感は、英語とは全く異なります。輸入ミュージカルでは、日本語の響きを最優先に制作することはできない。どうしても後手後手に回る形になります。
そういった意味では、日本語のオリジナルミュージカルを作る作業には、独特の楽しさがあります。日本語の音感が最高に活きるメロディを作り、そこに日本語ならではの語感を活かした歌詞を乗せられる。
ただ僕は、それを完全に活かしきっている和製ミュージカルというのは、まだこの世に存在していないんじゃないかと思っています。
――というと?
末満:日本語の語感を活かしきった上で、さらに題材や世界観をも完全にシンクロさせた作品。それは、日本のミュージカルの歴史においていまだ開拓されていない未知の領域なんじゃないかと思っているんです。もちろん僕が出会っていないだけの可能性もありますが。
そんな作品を作ることは、僕の目標のひとつです。人生の中で、会心の一撃と呼べるそんなミュージカルを一本、たった一本でもいいから生み出してみたい。
和田:僕の夢もそうですね。和製ミュージカルで、会心の一本。
とくにここ1〜2年ほどは、「そんなミュージカルを作りたい、今の自分にならきっとできる」という思いが強くなっています。
――思いが強まるきっかけが何かあったのでしょうか?
和田:僕はもともと、輸入ミュージカルに対してコンプレックスを抱いていました。最近まで「本場欧米の作品はやっぱり違う、敵わないな」という意識が頭のどこかにあった。
でも近年、日本や韓国の映画・ドラマがNetflixのような媒体を通じて世界的に評価されるようになってきましたよね。その状況を見て、「日本だからできないなんて言い訳だな」と自省するようになりました。
Netflixとそこで配信されるアジア系コンテンツがどんどん台頭してきたことで、これは欧米コンプレックスなんか抱えてる場合じゃないぞと。
末満:その感覚、よく分かる。Netflixには確実に価値観を変えられたよね。加えて、僕の場合はニューヨークのブロードウェイに足を運んだことも良い経験になりました。
和田:あ、僕もそう。Netflixとブロードウェイ。不思議なことに、ほとんど同じ時期にふたりともブロードウェイに行って、同じような経験をしたんですよね。
末満:示し合わせてもいないのに、なぜか旅行の時期がたまたま重なったんだよね。
僕は、ミュージカルの本場ブロードウェイで実際にいろいろな作品を見たとき、やっぱりすごいなと打ちのめされつつも「雲の上では無いな、頑張ったら届くかもしれない」という思いが込み上げてきたんです。
その後、韓国映画『パラサイト/半地下の家族』がアカデミー賞をとったことで、「英語圏には英語の作品しか通用しない」というのも自分の思い込みだったと証明されました。『イカゲーム』をはじめ、韓国ドラマも世界で続々ヒットしていますしね。
和田:作品は英語じゃなくていいし、活躍するために必ずしも海外で仕事をする必要はない、と思えるようになりましたね。
末満:なんだかNetflix称賛インタビューみたいになっているけど(笑)。
――配信サービスというシステム全般が、エンターテインメントに大きな影響を与えているということですね。
末満:言語と国境の壁を言い訳にしてはいけないと、しみじみ実感しています。
『ヴェラキッカ』、TRUMPファンへのメッセージ

――最後に、『ヴェラキッカ』やTRUMPシリーズのファンの皆さんに一言お願いします!
和田:いつも作品を応援してくださって、本当にありがとうございます。この先も末満さんと一緒に、会心の一撃をお届けできるよう作り続けていきますので、ぜひよろしくお願いします。
そして末満さんは、体調にくれぐれも気をつけてください。
末満:体調は、お互いにね!
関西の小劇場でポッと始めた作品が、TRUMPシリーズとしてこんなに長い間続けさせていただけたこと、本当に感謝しています。『ヴェラキッカ』のような大きな作品に発展できるとは、当時は夢にも思っていませんでした。ひとえにファンの皆さまのお力添えのおかげです。
これから、もっともっと面白いもの、新しいものを届けていきたいと思っています。僕たちも楽しんで作っていきますし、お客さんにも楽しんでいただけたら幸せです。
※※※
発売されるBlue-ray&DVDについての詳細は、こちらをご参照ください。
取材・文:豊島オリカ/撮影:梁瀬玉実/編集:五月女菜穂
広告
広告