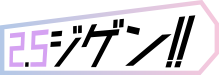朗読活劇「信長を殺した男 2021」が11月26日(金)~28日(日)、東京・神田明神ホールで上演される。
売上総数200万部以上を誇る歴史コミック「信長を殺した男~本能寺の変431年目の真実~」が“朗読活劇”として舞台化。脚本・演出は岡本貴也。原作コミックにはない新エピソードが登場する。
公演は「桔梗」「木瓜」の2通りで、「桔梗」には平野良(明智光秀役)、安里勇哉(織田信長役他)、横田龍儀(豊臣秀吉役他)、菊池修司(徳川家康役他)、相良茉優(光秀の妻・煕子役他)、「木瓜」には鈴木裕樹(明智光秀役)、古谷大和(織田信長役他)、宮崎湧(豊臣秀吉役他)、大崎捺希(徳川家康役他)、久保田未夢(光秀の妻・煕子役他)が出演する。
本記事では平野良、続く記事では横田龍儀と宮崎湧へのインタビューの様子をお届けする。両記事ともに貴重な話が盛りだくさんだ。
3度目の光秀役で受け取ったもの
――平野さんは過去にも明智光秀役を演じたご経験があるそうですね。
実は今回で3回目です。どれも“if(もしも)”作品ではあるのですが。本作は、台本を読んだ時に僕の中で一番納得した光秀のifだったので、携わることができてすごく嬉しくて、楽しみです。
タイトルに『活劇』とあるように、講談のような構成でお話が進んでいくので、一般的な朗読劇とは一味違っています。正直、語り部さんが大変だろうな…と(笑)。立ち位置がいくつも変わる重要なポジションだし、難しそうな印象でした。今、代役の方が演じてくださった動画を自宅で見ながら稽古をしているのですが、セリフの合間に三味線が入ったりする斬新な作りになっています。最近では講談師という存在が若い世代にも知られるようになったので、どの世代が見ても面白いと感じていただけるのではないでしょうか。
――明智光秀という人間を演じるにあたって、回を重ねるごとに印象の違いや気づきがあれば教えてください。
過去の出演作では(ある意味本作も)『豊臣秀吉が語った物語』が後世の史実として残っていて、真実かどうかは分からないけど、それが物語の軸となっていました。
本作のような正義がある光秀は(自分が思う)彼の像に一番近いなぁと。過去にも何度か光秀がどういう人物なのか勉強したり調べたりしたんですけれど、やはり「秀才で切れ者で裏がある」と言われていることが多いんですよね。今回、そのイメージがかなり覆されたけど、「真の光秀ってきっとこういう人なんだろうな」と自然と納得させられました。
――台本を拝見してみると、確かにこれまでのイメージとは大きく異なりますね。
そうなんですよ。快活というか、明るい人で。1時間半くらいの長さの朗読活劇なので、省くところは省きつつ、でも原作漫画の魅力的な部分はそのままに、光秀の自伝のような作りにはなっているのですが、「あれ? 光秀にこんなイメージって持ってなかったな、原作ではどんなふうに描かれているんだろう、読んでみたいな」という流れができています。メディアミックスとして、朗読劇と原作のどちらも、さらに広がっていってくれることを願っています。
本作って徹底的に裏付けが取られているんですよね。国内だけではなく海外の方が書かれた書物まで網羅して、しっかりとした考察のもと明智光秀を確立して。なんというか、すご過ぎて読んでいると『知ってはいけない真実』を知ってしまった気持ちになるんです。
――徳川家と豊臣家ももちろんですが、本作では細川家も鍵となってきます。
僕、実は10年以上前に、細川忠興役を演じたことがあって。めちゃめちゃパロディ作品なんですけども。チェックの衣装を着て歌ったりね(笑)。すごく個人的にではありますが「人生、全部繋がっていくなぁ〜」としみじみ感じてしまいました。
過去に演じさせていただいた他の歴史上の人物も、この原作を読んでからは「あの時は、こんな裏があるとは思ってもみないまま演じていたなぁ」と考える日々です。
歴史は後日談として語られたものが集約して成り立っているので、当時何があったのか、本当かどうなのか、その真実は現代を生きる僕たちには知りようがないんですよね。しかし「本作こそが真実なのでは?」と思ってしまうほど、本当に裏付けの説得力がすさまじいんです。
平野良の忘れられない“約束”とは

――ちなみに、都市伝説で多く語られるような「もしかしたら明智光秀は生き残って僧侶になっていたかもしれない」といった話にご興味はありますか?
いろんな伝説がありますよね。織田信長が実は本能寺の変以降も生きていたとか(笑)。坂本龍馬も然り。結構好きです、地方公演へ行ったときに史跡に立ち寄るくらいには。
あと、この“もしも”を舞台で表現できるというのはエンターテインメントの魅力の一つですよね。色々な解釈があるのはもちろんだし。歴史ものの面白さって、同じ人物なのに作品によって表現方法や見え方が違ってくる。いつ、どこで、誰が、その人物を見るかで印象は大きく変わってくるなぁといつも思っていて。
これは現代社会でも同じで。すごくいい人が裏ではすごく怖い顔を持っているなんてこともあるって聞くじゃないですか。その逆もあると思います。「なんだかあの人、苦手だな」と感じたとしても、他の角度から光を当ててみると本当はすごく素敵な人だったりする可能性もあるんです。
この、可能性を広げる考え方は、僕のこれまでの対人関係や人生にも通じていて、学ぶものがたくさんありました。そういったところが歴史もののいいところでもあり、奥深いところでもありますよね。「あ、こんな一面もあったんだ」ということにはチャンスとヒントが潜んでいて、相手を考察することによってお互いにプラスになるような効果が生まれるのでは、と考えます。
――本作で言うところの『煕子に会いに行くシーン』がまさに、光秀という人物の新たな一面を垣間見た気がしました。
そうですよね! 冒頭の、桔梗の花の…ネタバレになるので多くはまだ語れませんが。いいですよね。ザ・人間臭い、というか…そんなイメージ誰も光秀に抱いていなかったんじゃないか?ってくらい、一途で。まさに純愛ですよね。
若い時分に2人は出会っていて、しばらくして再会を果たすまで、光秀は30歳を過ぎても誰も娶らなかった。30代なんてあの時代なら今で言う60代くらいの認識だろうなっていうのに。その妻の存在があったからこそ彼は天下泰平を願った。信長を討った裏側には、亡くなった子供や妻との約束があり、それこそが出発点だったんですよね。『愛ゆえに』ということなんだろうなと思います。
今、そんな彼の持つ愛情深さやおおらかさを、本番の中でどうやって表現していこうかなと考えています。朗読劇は身体表現というよりは耳で聞いてどう感じ取るかが重要になってくるので、多角的に、役者が持つ色々な武器を使って挑んでいきたいですね。言葉一つ一つを大切に紡いでいかないと、ただ流れていってしまうだけなので。
――台本の中で印象に残っているセリフがあればお聞かせください。
先程おっしゃっていた煕子へ会いに行くシーンで、「そうか、私との縁組は本意ではなかったか。一回り以上も(歳が)離れておるしな、ははは」というセリフが哀しすぎて! 分かるんですよね、一回りも下の人にそんなことを言う切なさが! 「おじさん、頑張れ〜」みたいな(笑)。そりゃあ、そのセリフのあとにぼたぼた涙も出ますよね。詳しい経緯は本番でぜひ確かめてみてください。
でもね、だからこそエンディング間際の煕子とのシーンはすごく美しいんです。愛の結晶だと思う。それを経て光秀はもう一つの覚悟を決めるんですよね、自身の中で、「必ず約束を叶える」と。
改めて彼の器の大きや包容力を感じます。兵法を勉強して歌も詠める人だけれど、身分がどんどん落ちていって戦で負けて…そういった弱いものの立場を知っているからこそ、弱者のために自分が強くなろうとしたんでしょうね。大きな人です。みんなに慕われているけど『自分はあくまで補佐なんだ』というところが彼らしいというか…トップオタじゃないけど…あれ、なんだか光秀が“TO”に見えてきてしまいましたね?(笑)
――平野さんご自身にとって“忘れられない約束”はありますか?
かなり昔、高校生の時なのですが、僕は一度、芸能界から離れた時期があって。その離れる決断をする前後に、ある芸能人の方に相談にのっていただいていたんです。「いつか芸能界に戻ってきたら、めちゃくちゃ売れるようになるから、それまで俺のことを覚えていてね」とその人に伝えて、彼も「覚えているよ」と言ってくれて。
復帰して2〜3年後くらいかな? 別の撮影所でたまたまその彼に再会したんです。そこで「覚えてる?」と聞いたら「当たり前じゃん!」って返ってきて! それがめちゃめちゃ嬉しかったですね。今でも心に残る大切な、大切な約束です。
ファンへのメッセージ

――では最後に、ファンの皆さんへメッセージをお願いします。
信長や秀吉、光秀と、過去にこの武将たちが登場する別の作品に触れたことがある方も多いと思います。本作は物語自体がすごく魅力的なのはもちろんですが、「これこそが真実なのでは?」と思うような説得力を帯びた作品です。
豊臣秀吉は僕の大好きな武将なんですけど、本作ではすっごくいやらしい人物になっていたりします。そういった固定観念の崩壊や朗読劇の見せ方、テンポやリズム感、言葉の重みなど、あらゆる角度からの演出でこの物語をよりいっそう楽しんでいただけると思います。
タイトルだけ見ると、「もしかしたら難しいお話なのかも」と感じるかもしれませんが、僕はある意味、壮大なラブストーリーとして捉えていただいてもいいのでは、と思うんです。戦や駆け引き、厳しい局面もあります。しかし、この戦国時代だからこその純愛にも注目してみてください。よろしくお願いいたします。
* * *
平野のたくさんの想いが投影された本作、ぜひ現地で目に焼き付けていただきたい。
撮影・取材・文:ナスエリカ/ヘアメイク:SHIO
広告
広告